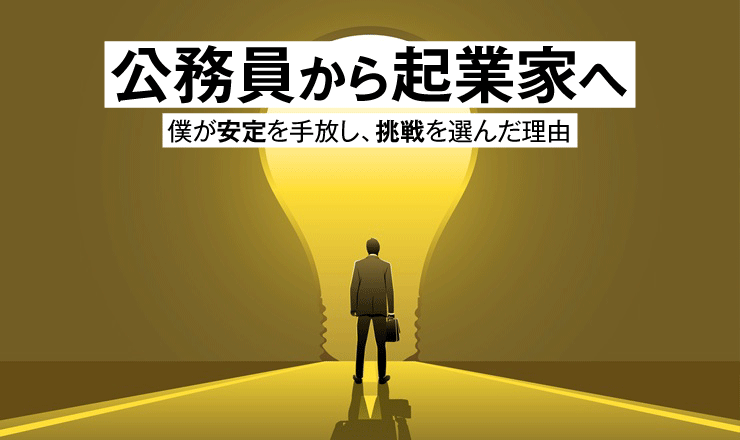フィラメント創業者の角 勝(すみ まさる)です。
フィラメントを起業したのは42歳のとき、下の子はそのときまだ0歳、上の子もまだ4歳のときでした。
でも「こどもが小さいのに思い切ったことしたね」といわれることはあまりありません。
なぜか?
僕の前職との落差の方が眼をひくからだと思います。
僕の前職は大阪市役所の職員、地方公務員です。
新卒で入庁(役所に就職するのは入社ではなくて入庁といいます)してからちょうど20年間を事務員として過ごし、その後起業するというのは珍しいキャリアだと思います。
世の中で一番「お堅い」職場から一番「柔らかい」職場へのシフト。そんな印象だと思います。
こんなキャリアを歩んでいるといつも聞かれる定番のFAQ的な質問があります。
それは
Q1. なんで役所に入ったの?
Q2. なんで役所辞めたの?
Q3. 奥さん反対しなかったの?
の3つです。
自己紹介がてら、回答していきます。
Q1. なんで役所に入ったの?
A1. 頑張れば入れそうだし、楽そうだと思ったから…というのが答えです。僕が大学を卒業したのは1995年、バブル崩壊後の就職氷河期です。文学部西洋史学科という当時の就職では著しく不利な学科に所属していた僕は、ガクチカも特にないですし、一般企業の就職は最初からあきらめて公務員試験にかけることにしました。地方公務員なら給料もそこそこ、福利厚生も充実していて転勤もない。おまけに残業も少なく仕事のノルマもないだろうと思って(実際は全然違うということを就職してから知るのですが)、市役所を受験しました。大阪市を良くしたいとかそういう意欲は一切ありませんでした。もちろん就職時の面接ではそうは言いませんでしたが。
Q2. なんで役所辞めたの?
A2. 役所を辞めた方が社会に貢献できる総量が増えると思ったからです。A1で答えたように、就職した時点ではホントどうしようもなく意識の低い人間でしたが、職場で尊敬できる先輩に恵まれ、仕事でもまれていくうちにずいぶんと意識が変わったと思います。仕事をすることで社会に貢献するという意識が5年、10年という月日をかけて醸成されていきました。
そして就職後15年目にさらなる意識の転換点が訪れます。
娘が生まれたんです。
生まれたばかりの娘を見て脳髄に電撃をくらったような衝撃がありました。
「この子がこれから生きていく世の中を、より良いものにしていくために自分は何か努力しているのだろうか?」
という問いが突然、頭に去来したのです。
僕は大学時代に西洋史学科に所属していたことは先ほど少し書きましたが、それは人間を知りたいと思ったからです。
僕はローマ史専攻でしたが、古代ローマって血生臭い野蛮な時代です。教育を受けるなんて特権階級のみだし、人間の尊厳は羽毛のように軽く、平等権も生存権も存在しない。
でも今、日本ではそんなことありませんよね。
世の中は信じられないくらいすごくよくなっている。
その影には世の中を良くするために闘ってきた人類の先輩たちがいて、その人たちの何世代にもわたる努力のおかげで僕たちは今の幸運な時代を生きることができている。
そう考えたときに、自分の「何もしてなさ」が恥ずかしくなったんです。
世の中を良くするための努力を何もしていないということは、自分が死ぬときに娘に胸を張って死ねないなと。
娘の誕生をきっかけに僕の価値観は大きく揺らぎ、「世の中を良くするために自分ができることをできる限りやる」ということを強く意識するようになりました。
「世の中を良くするためにできること」を考えようとすると、そもそもどうなったら「世の中が良くなる」のかを理解しないといけません。ですので、まずは自分の経験を増やすべく、いままでやっていなかったことをやり始めました。
当時出はじめていたFacebook、LinkedIn、Instagram、Twitter(現X)などのSNSはとりあえず全てアカウントを作ってみる、寄付型の投資をはじめる…といったこともやりましたし、何か商品を買う際にも、どれを買えば「世の中を良くする」ことにつながるのかを考えるようになりました。
Facebookアカウント: https://www.facebook.com/masaru.sumi
LinkedInアカウント: https://www.linkedin.com/in/sumimasaru/
日常生活上で意識できる「世の中を良くする」が習慣として馴染んでくると、仕事でももっとプロアクティブに「世の中を良くする」ことができないかと考えるようになりました。
そんな矢先に目に入ったのが、役所内の新規事業提案制度(正式には職員提案制度)でした。
これは面白そうだと思い、応募してみました。
準備にはそれなりに時間がかかりましたが、初回応募したものが入賞(審査員特別賞)し、その翌年に応募したものも入賞して、当時の橋下徹市長にもお褒めいただきました。
これがあってから「あ、僕は新規事業を考えるのは得意なんだ」と気づき、その後、イノベーション推進部門へ異動させてもらうことになりました。
このイノベーション推進部門では、大阪イノベーションハブという施設の立ち上げと運営を経験することになります。
大阪イノベーションハブは行政が運営するオープンイノベーション施設であり、おそらく日本でも最初くらいの取り組みだったはずです。当時は行政が運営するハコモノは基本失敗するといわれていて、ましてやイノベーションなど最も役所と相性が悪い領域、かなりリスクの高い取り組みだったと思います。
ですが、多くの役所外の方々に関心とご協力をいただけたことで、大きな成功を収めることができました。
この大阪イノベーションハブの活動に携わる中で、自己効力感が高まり、「新しいビジネスをつくっていく活動」こそが自分の天職だと感じるようになりました。
しかし、いずれ人事異動があるーというのが役所勤めの悲しさです。せっかく見つけた天職も人事異動があれば手放す必要が出てきます。
僕にとってそれはとても耐え難いことでした。なので、人事異動がくるまえに「辞めるための下準備」を進めていました。
ある程度その下準備が進んだ頃、『週刊ダイヤモンド』で取材され、それを一つのサインと捉えて退職することを決断した…という流れです。
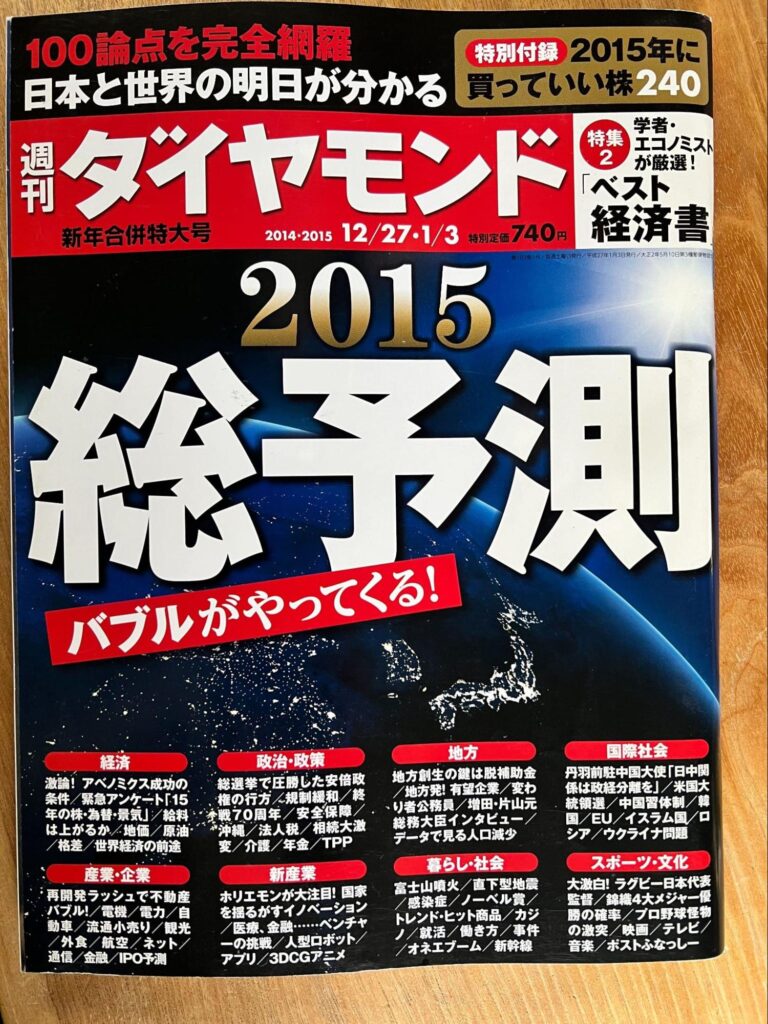
この頃には役所を辞めて自分で会社を作った方が自分の才能や能力を100%傾注することができるし、それによって社会に貢献できる総量は絶対に増えるはずだ…という確信を持つことができていました。この自信がなければ起業するには至れなかったかもしれません。
Q3にも答えようかと思いましたが、ちょっと長くなりすぎたので次回のネタにすることにします。