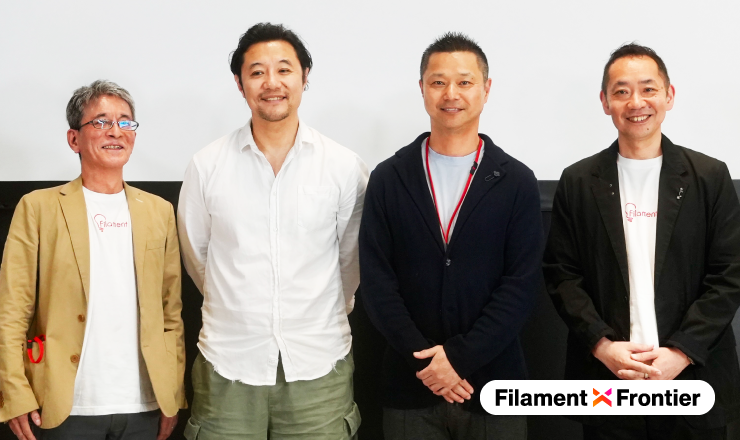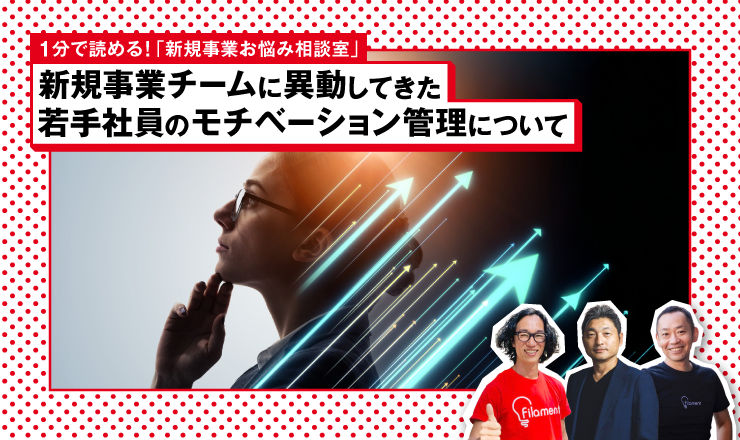福山発のグローバル企業、常石グループ
宮内: 今回のセッションテーマは「地方グローバル企業が語る新規事業人材育成事例」です。このセッションでは「新規事業」について、特に地方で実践されている方々の取り組みや、地方でどう人材を育てていくかといったテーマでお話しできればと思っています。今回登壇された津幡さんは、広島県福山市にある常石商事にお勤めで、フィラメントでも支援をさせていただいています。今日はそういった地方に根ざしたリアルなお話を中心に伺えればと考えています。まずは、常石グループがどのような事業を展開されているのかについて、津幡さんからご紹介いただければと思います。
津幡:はい。常石グループは広島県福山市に本社を構えており、海運から造船に進出して、エネルギー、産業廃棄物処理、地域のモビリティ、観光、ホテル事業など多岐にわたる事業を展開しています。地域に根差したローカル企業に見えて、実は船の製造の約8割はフィリピンと中国にある造船所で行っています。海運事業は中国やシンガポール、ヨーロッパやインドに拠点を持ってグループ企業を展開していて、未上場企業ながらグローバルなビジネスを展開しています。

入山:船も自分たちで作って自社で運用してるんですよね? 海運業者って普通は船を借りることが多いと思うんですが。
津幡:その通りです。自社で製造して所有している船もありますし、外部から借りている船もあります。
入山:日本の造船ってかつては世界一だったけど、今は韓国や中国との競争が激しいですよね。常石さんはどのように国際的な競争力を維持しているんですか?
津幡:現在、製造の約8割はすでにフィリピンや中国で行っているため、いわゆる労働コストの差という点では、あまりないと思います。一方で、近年は環境対応型の船舶、例えば新しいエネルギーを活用した船や、燃費性能の高い船に関しては、一定の技術力があるという自負はあります。こういった分野であれば、ある程度のポジションを確保できそうだという手応えも感じています。
入山:なるほど。これからは完全に船の時代なんですよ。だからこそ今、船を製造できている状況にあるというのは今後強いんですよね。
地方から一気にグローバルを狙う
宮内:続いて、地方にある企業がなぜ新規事業の展開や人材育成においてポテンシャルを持っているのかについて、議論を深めていきたいと思います。まず角さん、どう感じられていますか?
角: 僕の出身の島根県出雲市は過疎化が進んでいて、「辺境」とも言える場所です。でも、だからこそ新しいことがやりやすい。例えば出雲地方は厚労省の医療系の実証実験がすごく多かった。人が少ない分、既得権益層や抵抗勢力も少ないので、前例がないことでもスムーズに動ける、言わば「ナチュラル・サンドボックス」なんです。
入山: 同感ですね。日本は課題先進国ですが、一番の課題は東京ではなく地方にあるので、地方が一番イノベーション起きるんですよね。東京のような既得権益もないし、面白い人が地方に移って面白いことやったらどう見ても良い。しかもネットの時代なのでグローバルに簡単につながれる。日本は地方から一気にグローバルに行っちゃうのがどう見ても勝ち筋なんです。
津幡:そうですね。私は今から約10年前に常石グループに転職したんですが、それまでは東京生まれ・東京育ちで、主にコンサルティングやIT業界にいたので、地方とはまったく異なる環境で仕事をしていました。そんな中で気づいたのは、入山先生がおっしゃっていたことと同じで、地方にはいきなりグローバルに展開できるような新規事業の可能性があるということです。実際、うちの造船業自体がそうで、広島県福山市で始めた事業をフィリピンに展開した結果、今ではフィリピン最大の造船所になっています。このように、生産を含めて海外へダイレクトにつながるのは、十分にあり得ると感じています。 ただ、福山のように経済的に比較的豊かな地域では、逆に「なぜ新しいことをやらないといけないのか」が見えづらい。JFEの西日本最大の工場があったり、青山商事や福山通運もあって割と豊かな町なので、若い人が新しいことをやらなくちゃいけない理由がない。既存の枠組みの中でそこそこ生活できてしまうから、新たな挑戦に向かう危機感が生まれにくいんです。我々が海外に出たときは「中国や韓国に追い上げられて日本の製造コストだとやっていけない」という危機感があって、海外進出しないとサバイブできなかったんですよ。
角:福山って、広島とも岡山ともまた違う独特のカルチャーがあって、良くも悪くも「純粋培養」された空間なんですよね。それがラボ的で面白い実験場にもなる。変化に敏感でない分、実験的なことがしやすい環境とも言えます。
入山:「辺境の方がイノベーションが起きやすい」というのは研究の観点から見ても明らかなんです。東京は人が多すぎるから同質化するけど、辺境は同質化しないから、変なアイデアのままでも簡単につき進めるんですよね。イノベーションはいわば「変なアイデア」なので同質化すると出てきづらいんです。 実際、明治維新だって山口や鹿児島など地方から起きたわけで、地方の「語り合う文化」や「暇」がイノベーションを生む要素でもある。その点、東京だと一発ビジネスを当てて上場して小金を持つと西麻布で女子と合コンしてるんですよ(笑)。だから地方の方が絶対良いです。

越境体験で真面目な社員のマインドを変える
宮内:ここからは本セッションのもう一つのテーマである「人材育成」についてお話を伺います。津幡さん、現在抱えている課題や取り組みについて教えていただけますか?
津幡: 4年前くらいから、グループ内で「新しい事業が長らく生まれていない」という課題感がありました。それまで新規事業はオーナーファミリーのトップダウンで進んできたのですが、従業員発の新規事業を生み出したいという方向にシフトしています。新しい時代の変化に適応するには、社員自身の中からアイデアが出て、それを形にする力が必要だと考えたんです。
そこで、外部の専門家であるフィラメントさんと連携し、将来の幹部候補や意欲的なメンバーを選抜して、8か月間にわたる実践的な研修プログラムを開始しました。3年前に初めてやってみたら、いろいろな刺激を受けたようで、元の部署に戻っても、現場の上司から「一皮むけた」「変化が目に見える」といった評価が寄せられ、新規事業そのものに取り組んでいなくても社内でも良い影響を及ぼしたんです。それ以降、毎年10人ずつくらいがプログラムを受講しています。今は「新規事業ってどう考えたらいいのかわからない」という人が多いので、ポテンシャルがありそうな人たちを探して、スタートの第一歩を植え付ける。そのあとに、本当にやりたい人をいかにサポートしていくかというフェーズに入り始めているというところです。
角: 僕が見ていて感じるのは、「真面目」な人が多いこと。言われたことはしっかりやるけど、自ら未来を構想したり、新しいことに興味を持ったりするマインドがまだ育っていない。それを変えるには、単なるスキル教育ではなく、マインドセットの転換を促すような環境と体験が必要です。
津幡: 確かに、ヤフーなどでは、日常の中で「これ面白いよね」「こんなサービス真似できない?」といった雑談が飛び交う環境がありますよね。でも福山では、そういう会話自体があまり生まれない。言ってることを肯定はするんですよ。でも部下が上司に「御意」と言うようなやりとりは都会以上にある感じがしますね。自分としてはもうちょっと話を膨らませたいんだけど膨らんでいかない、みたいな。
入山: 人のマインドって、基本的には変えようと思ってもなかなか変わらない。でも、変わる「きっかけ」を与えることはできる。例えば、外部から来た“ちょっと変わった人”が、自由に楽しく新しいことを始めると、周囲の人たちが自然と刺激を受けて、自分も何かやってみようという気持ちになる。そういう予想外の存在が社内の空気を変えるんです。
津幡: まさにそうですね。実際に、今、社内のイントレプレナーとして「フィリピン人材ビジネス」のリーダーがいるんですが、彼が積極的に行動する姿を見て、「あの人すごいですね」と自然に周囲から声が上がるようになりました。これまで空気を読んで積極的に動けなかったような社員も、少しずつその影響を受けていると感じています。これは、小さな成功体験の積み重ねによって、組織の文化が変わっていくプロセスだと思います。
角:フィラメントではマインドのトレーニングも提供しています。意識してやっているのは、できるだけ越境になるような体験をしてもらうということです。例えば別の会社で新規事業をやっている面白い人の話を聞かせるとか、近畿大学の学生起業家のピッチを聞かせた上で彼らにピッチしてもらうとか。目線が養われていると、自分たちがやっていることよりはるかに学生の方がすごいってわかるんですよね。「学生なのになんでこんなにできてるの」という感じになる。普通に聞くだけだと何を言ってるのかわからなかったり、そのすごさが理解できないんです。ただ、自分も活動していると、その顧客の課題をよく発見したなとか、仮説検証の長い道のりをよく粘り強くやったなとか。自分の行動としての当てはめをするからすごさを認識できるんですよね。
宮内:「越境体験」を通じて、これまでの環境では得られなかった視点を取り入れることが、人材育成の大きな突破口になるということですね。社員の意識が内向きになりがちな地方企業だからこそ、こうしたアプローチは非常に意義深いと感じます。

宮内:最後に、越境体験をどうやって促していくべきなのかについて一言ずついただけますか。
角:非認知能力に関する本を読んでいると、「好奇心」も非認知能力の一つ、つまり“能力”として捉えられていることがわかります。 そして、能力であるということは、トレーニングによって鍛えることができるということでもあり、本人が自分で体験し、試行錯誤しながら体得していく必要があります。 だからこそ、私たちができるのは、そのプロセスにどれだけ寄り添えるかということなんだと思います。「寄り添う」とは、例えばその人が自分の経験を咀嚼するのを手助けしたり、内省を促したり、意味づけや解釈のプロセスを支援してあげることです。最初はなかなかうまくできないかもしれません。 でも続けていくうちに、少しずつ解釈できるようになってくる。 そしてその積み重ねの結果として、起業家のピッチを聞いてそのすごさを理解できるようになるのだと思います。
津幡:少し遠回りに思えるかもしれませんが、やはり若手のうちからできるだけ外の世界に目を向けさせること、そして会社の文化そのものを少しずつ変えていくことが、実は一番効果的なのではないかと思っています。 そして「越境体験」と呼ばれるような機会を提供すること――つまり、自分の枠を越えて外と関わるような体験を用意することは、積極的にやっていく必要があります。加えて、「こういうことは価値があることだよね」「だからこれくらいの比率で取り入れたいよね」といった、分かりやすい目標への変換も重要です。例えば、「スタートアップへの出向を年に○人実施する」といった具体的な目標を経営計画に組み込む。 さらに、それを「人的資本経営の一環として実施する」「多様性を広げる取り組みとして位置づける」など、会社全体の方針にうまくつなげていく。そういった方向づけをしていくのは、まさに今日ここにいらっしゃるような方々が担っていくべき大事な役割なんじゃないかと思います。
入山:越境体験について、たぶん一番大事なのは「繰り返すこと」だと思うんです。いちばん危ないのは、ある大企業が「これからは人材育成だ!越境体験だ!」と意気込んで、フィラメントに頼んでドーンと1回だけ大がかりなプログラムをやって、「よし、やったぞ!」と満足して終わってしまうパターン。 で、帰ってきて「はい、越境完了!」と言っちゃう。これは最悪です。本当に大事なのは、「繰り返す」ことなんですよ。
だから、「越境」を生活の一部として当たり前にしていく――これがすごく大事なんです。最近よく耳にする「リスキリング」という言葉も、僕は少し危ういなと感じていて。 どうしても「一回研修を受けたらOK」みたいな扱いになりがちなんです。 それって本質からズレていて、本当はもっと“派手に”やるべきなんですよ。 僕は最近、「リスキリング」じゃなくて「転生しろ」って言ってます(笑)。 もう“メタモルフォーゼ”です。生まれ変わるレベルで。越境を繰り返すことで、どんどん自分を好奇心を持って生まれ変わらせる。これからのAI時代、そういう人しか生き残れないと思ってます。

プロフィール
・入山 章栄(早稲田大学ビジネススクール教授)
・津幡 靖久(常石商事 代表取締役副社長)
・角 勝(フィラメント 代表取締役CEO)
・モデレーター:宮内 俊樹(フィラメント フェロー)