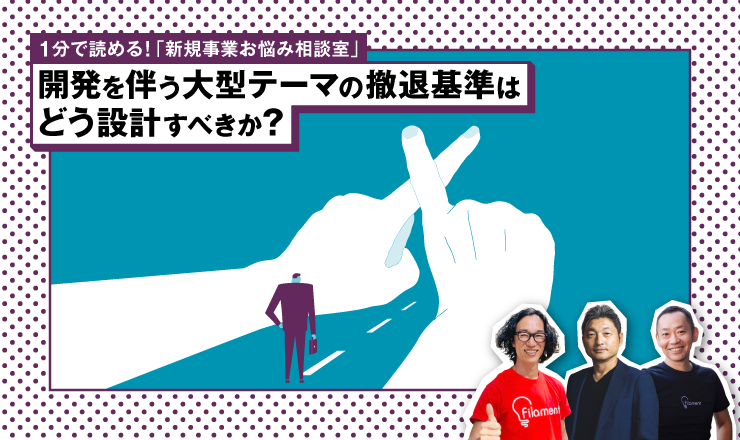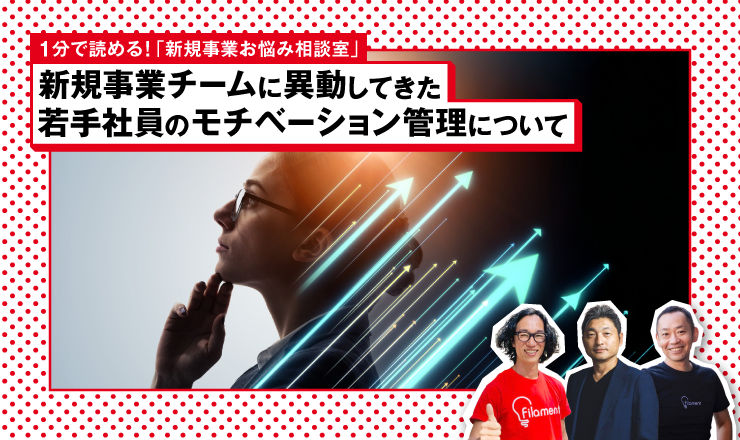フィラメント公式YouTubeチャンネルでは毎週水曜日に『新規事業お悩み相談室』を配信しています。この番組では、実際に新規事業に携わっている方々からお寄せいただいた質問やお悩みに、数々の新規事業の現場を見てきたスペシャリスト村上臣さん、グローバルなスタートアップ投資家として有名なリブライトパートナーズの蛯原健さん、そしてフィラメントCEOの角勝が相談員として回答しています。
本記事では、動画で配信している『新規事業お悩み相談室』を1分で読めるダイジェスト版としてお届けします。
今回いただいた相談は「経営層の期待と現場の停滞を乗り越える新規事業推進の課題」です。
質問者:
中堅住宅不動産会社・Cさん
相談の背景や理由:
社内新規事業プログラムの事務局を担当しています。住宅市場の停滞を受け、既存の強みを活かした新サービスの立ち上げを指示され、複数のチームで年間スケジュールに沿ってアイデア創出からPoCまで進めています。しかし、進捗が遅れ、経営層への報告のたびに新たな指示が加わり、方向性が定まりません。経営層の期待にそのまま応えると既存事業とたいして変わらなくなりそうです。プロセス改善や会議の見直しも試みましたが、モチベーションの統一ができず計画通りに進みません。どうすれば期待に応えつつ事業を推進できるでしょうか?
角:本日の質問は中堅住宅不動産会社Cさんから、「経営層の期待と現場の停滞を乗り越える新規事業推進の課題」についてですね。このテーマは結構近い内容が何度か出てきていると思うんですけれども、その辺は村上さんの専門領域みたいになってきつつありますが、いかがでしょうか?
村上:相談者さんの苦悩がつたわってきますよね。ご愁傷様です。たしかに何度か似たようなご相談をいただいてますよね。その度に僕が言ってるのは、「上層部との握り」なんですけど、やっぱり事務局の方の立場ってすごく難しくて、上層部と現場に挟まれちゃうっていうところがありますよね。
「これって何のためにやってんだっけ?」って言われて、レポートとかにまとめて提出したら、「いや、ちょっと思ってたのと違うんだよね」みたいなことを言われるってことが多分あると思うんですよ。ただ、事務局の立場として整理をするのはやっぱり大事で、「最初に期待値を合わせる」という作業は今からでも遅くはないと思うので、「このプログラムの後にどういうものが出たらこれは成功である」という部分について恐れることなく上の人と話す、場合によっては上司の人に頼むっていうのも手だと思います。 要は、1年後にどういう成果が出ていればこのプログラムは成功って言えてもらえるのかというのがキークエスチョンだと思います。たとえば、「新規事業のアイデアが何個か出て、何個かスタートしてる状態」みたいな定義されたら、そこが期待値じゃないですか。
角:なるほど。
村上:そうであれば、現場に対しても「このアイデアが通ったら本当に進める気だよ」と伝えられて現場のモチベーション上がりますよね。で、あとはその中間のマイルストーンです。そのために逆算していくと、その会社によって新規事業を始めるには1年かかる、2年かかる…などなど規模によっても違うでしょう。 人員もちゃんと当てないといけないといったところも考えた時に、現実的にどういうタイムラインでやればいいのかという見通しを最初に上層部に見せて、「こんな感じでイメージ合ってますか?」というのをちょこちょこ差し込んでいくしかないんですよね。
質問の中で気になるのが、「進捗が遅れ、経営層への報告のたびに新たな指示が加わり、方向性が定まりません」という部分で、まさにここが握れてないなって思うとこなんですよね。多分、1発目の進捗報告の時にまだ期待値がずれている状態なんだと思います。上層部からすると「いくつか有望なアイデアが出てくるんでしょ」って思ってたのに、アイデアが全然出てこなくて、今みんなで考えてますってなったら、全然進んでないじゃないかみたいに言われちゃうじゃないですか。こういう場合は、たとえば「 この半年間はいいものも悪いものも含めてアイデアの数に集中してます。現在出ているアイデアは54個です」って伝えたら、「お、アイデアが結構出てるじゃないか」ってなるじゃないですか。そうして、このあとはこうなる予定ですって都度都度すり合わせをしていく期待値を下回らないようにしていくってことを事務局の方がやんなくちゃいけないんだと思うんですよね。
角:なるほど、なるほどね。今の村上さんのコメントの中にあった、フェーズによってKPIが変わるはずだからその都度のKPIに注目させる、つまり、視線をどこに誘導させるかっていうところもすごい大事なんだろうなって思いましたね。
村上:そこはすごく大事です。毎回会議の冒頭5分でマイルストーンや前回の振り返りを必ずする。「始まった当初はこれで皆さん合意して、今はここでこれやっていて、こういうKPIで見ています」みたいに進める感じですね。
角:毎回、前回の情報共有に5分ぐらい使ってちゃんと全員の目線合わせをやらないと、どんどんずれていくよっていうことですね。だから前提条件の共有をして、それによってガントチャートとかも、なるほどなと思いながら見られるようになる。やり方としてはスタンダードですが、定例になるとスキップしがちなところをちゃんとやるってことは結構重要なテクニックと言えそうですね。
村上:あとは、細かいテクニックとしてはツッコミどころを必ず何個か用意しておくっていうものです。報告を聞いてもらうだけで終わってしまって、「結局何も起こんなくて終わったな…、でも後で考えてみたらあれってどうなんだ。いや、違うんじゃねえか?」みたいになってまた横槍が入るなんてことがないように、会議中のエンゲージメントレベルを高める策としてやっぱり参加させるというのが1番いいわけです。
角:なるほど。たとえば部長がなにか意見を言って、「次回までに考えてきます」となって、次回その対策を考えてきたら、「俺の意見を活かしてくれた」みたいな感じの気持ちにもなりますね。
村上:そうすると、当事者意識が芽生えるんです。
角:それをきっかけに、「俺の言うことを尊重してやってくれたから」みたいな感じで、味方になってくれる人もいるかもしれませんね。
村上:そうそう。そこもネットワーク作りに活かしちゃって、「ちょっとそれ個別にミーティングで相談してもいいですか?」みたいにして、 アポを取っちゃったりとかするっていうのもありますよね。
角:今日はひときわ村上さんのプロサラリーマン力が見えてる感じがしますね。
村上:そうですね。プロサラリーマン経験としてのアドバイスと捉えていただいていいんじゃないでしょうか(笑)。
角:孫さんに鍛えられるとこうなるのかと思いましたね。
蛯原:もうほとんど付け足すこともないような感じもしますが、質問をよく読むと色んな悩みが散りばめられてるんですよね。進捗が遅れてます・毎回経営層が違う指示を出してきます・そのために方向性が定まらなくて困ってます・モチベーションが統一できませんと色々あります。その中で、最終的に何を聞いているかというと、期待に応えつつ事業を推進する方法なわけです。これ、結論としては、「良い新規事業ネタを誰かが考えて、 それを経営者が気に入ったら一丁上がり」っていうものとお見受けしました。それがなかなかできてないので、議論がグダグダ続いてる煮詰まり感を勝手に想像しました。
したがって、そういう時に何が必要かっていうと、よく英語でアウトオブザボックスって言いますけど、常識に囚われないことです。今までの議論の方向性とか、あるいは空気を読んだりしないで、ゼロベースで考えるということをやったらよろしいんじゃないでしょうか。 その場合のフレームワークとして、本業に近いとか本業とのシナジーってところがあるんですけど、それを突き詰めてしまうとただの本業になってしまうわけです。「それ新規事業でもなんでもないじゃん」となってしまって、それならお客さん1人でも捕まえるために営業してこいって話になっちゃうんですよね。
その逆がフロンティア投資、フロンティア探索になるわけなんですが、普通の経営者さんってあんまりお好きじゃないんですよ。それは飛躍しすぎ、シナジーがない、なんでうちがやらなきゃいけないんだって話になるんです。だから、やっぱその中庸が良いかなと普通の経営者の人は考えるわけです。ある程度本業と関係があったり、別事業だけどドメインは一緒とか、別プロダクトだけど販売網は活かせるとか。
一方で、事業化までの時間軸も大切です。最も手っ取り早く実現するのはM&A(買収)なんですが、日本企業は比較的苦手で、グローバル企業はバンバンやっちゃうみたいなところがあります。それに対して、1番時間がかかるのが、実は新規事業開発なんですよ。だから、「フロンティアとシナジーの真ん中ぐらいである程度のシナジーも効かせられる」「外から持ってくるM&Aと内で作る新規事業開発」という2軸のクロスした部分に位置するのが、スタートアップとの連携・前乗り切り投資って言われています。買収までは行かなくて、そんなに予算もかからないけど、ある程度投資に予算を割いて、スタートアップには自社にないものを求めて協業することで新しいものを作りましょうというものです。スタートアップじゃなくて他社との協業でもいいんですけど、ちょっと前提を取っ払ってお考えになるのもいいんじゃないかなと思います。もしかしたら上層部の要望にジャストミートするものもその辺にあったりするのかもしれないので、そういったアプローチも考えてもいいんじゃないかなと思いました。
角:新規事業を進めてきた上で煮詰まってきているのであれば、目線を変えてフレッシュにいろいろ提案してみるということですね。たしかに、今までと違う考え方を聞くとそういうのもあるよねみたいな気持ちにはなりやすいですよね。
蛯原:そうですね。協業は事業開発の延長でもあるので最初から否定する必要もないと思いますし、それによって時間軸が早まることで、経営陣がイメージする時間軸に少しでも近づくのであれば選択肢としてありじゃないかと思います。
角:少なくとも、こういう方向性もあるんじゃないですかという提案をすることで、 経営層が何を求めているかといった部分のコメントもどんどん引き出せて情報量が増えることは期待できますね。「実はこっちだったんだよ」みたいなのがあれば、煮詰まった状況も改善されて、進むべき方向も定まるかもしれません。
今回もお二人からさまざまな観点でアイデアをいただきましたね。中堅住宅不動産会社Cさん、ぜひ参考にしてみていただけたらと思います。
回答のまとめ
1.新規事業推進における経営層と現場の課題:
・期待値のすり合わせと明確なマイルストーンの設定
・進捗報告における視点の誘導とKPIの段階的な管理
・経営層の当事者意識を高める会議運営戦略
2.新規事業開発のアプローチ:
・本業とのシナジーとフロンティア探索のバランス
・スタートアップとの連携や他社協業による新規事業創出
・M&Aや投資を含めた多角的な事業展開の検討
今回ご紹介した内容は、以下のリンクから動画で視聴できます。
本記事では要約をお伝えしましたが、テキスト化できなかった部分もありますので、回答のフルバージョンをぜひ動画でご覧ください。