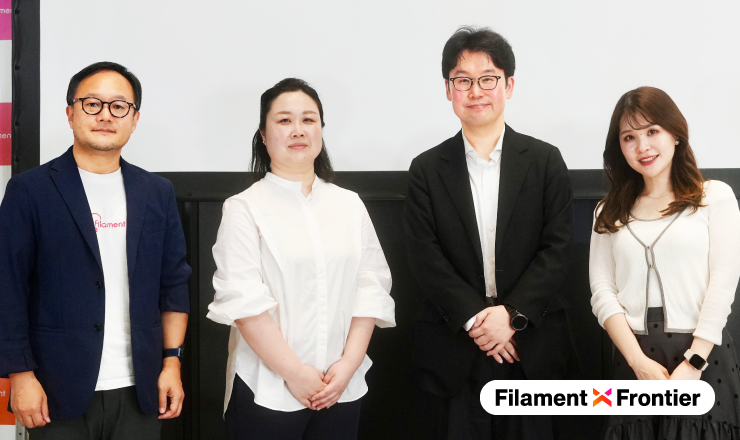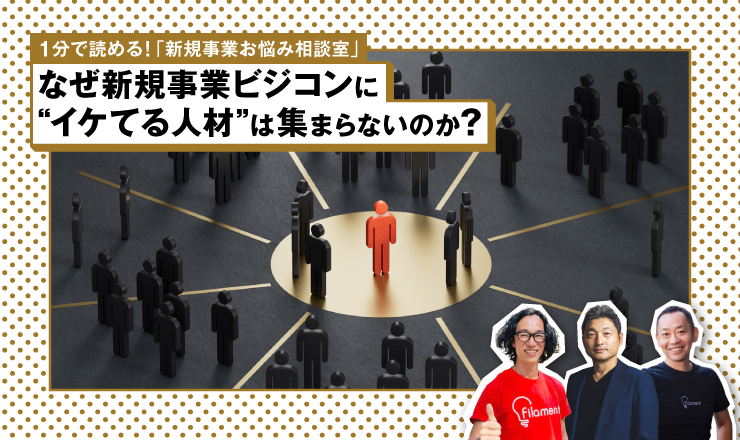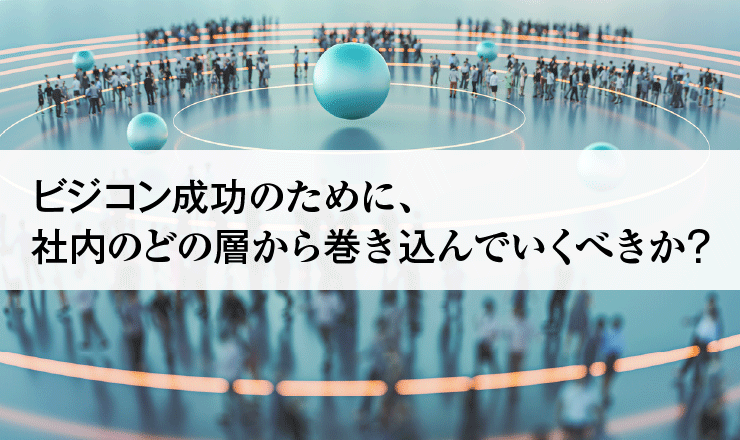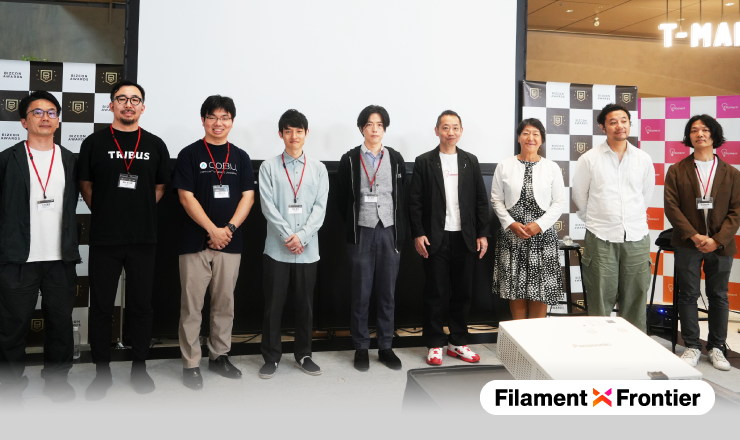社内ビジネスコンテストの目的「人材の発掘」「育成」「企業風土の醸成」
田中:セッション2では「社内ビジコンが大企業に与える影響とその価値」について皆さまとお話していきたいと思います。まずは登壇者の皆さんに自己紹介をお願いします。
井上:関西電力の井上です。関西電力入社後は火力事業本部に配属されまして、技術屋として入社しました。そのあと、社内起業制度SPARKにてYaala株式会社を設立しまして、去年クローズして、現在はイノベーション推進本部にて、新規事業創出に関わる人材育成を担当しています。本日はよろしくお願いいたします。
田中:今回の社内ビジネスコンテストのテーマについて、井上さんはかつて参加者としてスタートされ、現在はその経験を活かし、参加者や関連人材の育成に携わっていらっしゃるということですね。ご自身で一度事業を立ち上げられた経験も踏まえ、本日は貴重なお話を伺えることを楽しみにしております。続いて、北瀬さんお願いします。
北瀬:ヤマハの北瀬でございます。私は32年間、NECで事業開発と営業に携わってきました。最初の約20年間は、大学や小中学校向けの営業と事業開発を担当し、そして数字を背負いながら新規事業開発にも従事しました。その後、約10年間はコーポレート部門で事業開発を行い、9社のスタートアップやジョイントベンチャーをおこして、125億~130億円のファンディングに成功し、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の再編も手がけました。最後の2年間は、ヘルスケアとライフサイエンス分野の全体統括を担っていました。
良い区切りができたので、次は何をしようかと思った時に、これまでのIT分野での水平・業界横断の経験を活かし、次は垂直・業界特化に挑戦したいと思いました。そんな時、ヤマハとのご縁があり、未知の分野へ飛び込むという「ドM根性」を発揮し、現在新たな挑戦に向けて日々取り組んでいます。
田中:北瀬さん、ありがとうございます。現在、経営に近い立場で社内ビジコンや新規事業開発に携わっておられるとのことですので、ぜひその視点からのご意見やコメントをいただきたいと思います。では、最後に、東急不動産ホールディングスの久保さん、お願いいたします。
久保:東急不動産ホールディングスの久保と申します。私は最初の配属ではデベロッパーとして分譲マンションの計画を担当していました。その後、現在のCXイノベーション推進部に配属され、今年で4年目になります。ここでは運営事務局のような業務に携わっています。
CXイノベーション推進部は新規事業の創出をミッションとしています。その手段の一つとして、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の出資やスタートアップとの連携に加え、新規事業提案制度である社内ビジコン「STEP」の運営も行っています。この社内ビジコンの特徴は、最終審査を通過すると会社化するという点です。これは応募者にとって新たなキャリアステップとして、リーダーシップや経営ノウハウを習得する機会を提供することを目的としています。フェーズは大きく分けて「応募期」「事業化検討期」「事業化」の3つで構成されています。最初は業務時間外での活動となりますが、その後業務時間内で本格的に事業検討を進めることができ、最終審査を通過すれば会社設立へと至る仕組みになっています。

田中:久保さんはまさに社内ビジコンを運営する事務局の立場で活躍されているということで、その立場でのご意見などいただけるかなと思っております。ここからは、今自己紹介いただいた皆さまと、わたくしフィラメント田中の4名で進めさせていただきます。
セッションテーマは「社内ビジネスコンテストが大企業に与える影響とその価値」ですが、じゃあそもそも「社内ビジコンは何を目的として実施するのか」ということを登壇者の皆さまに事前にお伺いしたところ、シンプルに意見がまとまりました。社内ビジネスコンテストを実施する目的は、事業創出、人材の発掘・育成、企業風土の醸成の3点に集約され、これらを通じて企業価値の最大化を目指すというものです。今日はこの各テーマに沿ってお話をお伺いできればと思っております。
そもそも社内ビジコンを何のためにやっているのか
田中:まずは、社内ビジコンにおける「事業創出」の部分について北瀬さんにお話を伺ってみたいと思います。
北瀬:経営的な観点から見ると、新規事業、特に社内ビジコンは経営効率が良くないですよね。社内ビジコンだからというよりも、そもそも新規事業って投資に対するリターンってやっぱり確率論で言うと悪いですし、既存事業への投資の方が確実なリターンが見込めます。しかし、企業価値の最大化には、現在の収益性と将来の成長性の両軸が不可欠です。新しい挑戦を続けることで成長への機運を高め、量の中から質の高いヒット事業を生み出す必要があります。
また、社内コミュニケーションが良好な企業であればビジコンなしでも良いアイデアは生まれますが、多くの企業が抱える人事異動の困難さや受け皿不足といったボトルネックを解消するショートカットとして、ビジコンは機能します。社内外との連携を通じて新たな事業を生み出す期待値を高め、企業価値向上に貢献することが、ビジコンの期待値だと感じています。
入口と出口でのスケーラビリティ意識
田中:会場の皆さんにも「多くの企業が抱える様々なボトルネック」という部分で結構頷かれている方が多いなと思いました。登壇者の皆さまは、こういうボトルネックはあったけどクリアしたとか、今まさに大変だといったご意見ってありますか?
井上:私の場合は事業としてのスケール確立は達成できませんでしたが、社内ビジコンで新規事業を立ち上げる際、個人ではなく企業として取り組むため、スケーラビリティが強く求められました。最初から巨額の利益を出すことはなくとも、最終的にはそれが求められるため、それを実現できる事業を構築するのは難しかったですね。
久保:弊社でもスケーラビリティの観点はかなり重視しています。というのも、最終的に会社として設立し、資本金を渡す以上、事業がスケールしていくことは制度として明確に定めているからです。ただ、新規事業は利益だけでなく、ブランド貢献などの会社への多角的な貢献も重要だと考えています。そのため、数値目標だけを追うのが正しいのかという葛藤も生まれていますが、制度上は数値目標をしっかりと置いていますね。
田中:なるほど、ありがとうございます。特に大企業の皆さんですと、1億円の売上では企業全体から見ると微々たるもので、10億、100億、1000億円といった規模が求められるということですね。
北瀬さん、経営的な観点では、事業化を目的としたビジコンは最初からスケーラビリティを求めていくべきだと思われますか?
北瀬:スケーラビリティは、最初の事業が成功した後のストーリーやシナリオによって生まれます。最初の成功がないのに、その先の論理的なスケーラビリティを説明しろって言っても無理ですよね。ただ、壮大な構想を描いていても、実際に検証や投資、事業開始へと進むにつれて、市場規模が半分以下に縮小していくのが現実です。たとえば、最初に期待する事業規模が小さく、最終的にも数億円となってしまうと、「やる意味があるのか」と疑問視されかねません。そのため、スタート時には大きなビジョンを期待します。そのビジョンに対し、確実性や厳密な論理を求めるのではなく、まずはそのビジョンに向けて「どのような事業を、どのような顧客に、誰をターゲットとして展開していくのか」を検証して進めていこうという感じでしたね。
田中:なるほど。つまり、最初は確実な成長シナリオよりも大きなビジョンを描くことが重要であると。事業化のフェーズに進むにつれて現実が見えて規模が縮小することは織り込んだ上で、最初から厳密なスケーラビリティを求めるのではなく、途中で変化することを許容する柔軟な姿勢で始めることが大切ということですね。
人材の発掘・育成の側面
田中:次のテーマに移りたいと思います。新規事業の創出は非常に難しく、成功確率は低いと言われています。そのため、多くの企業が新規事業目的でビジコンを実施していますが、実際に新たな事業の柱が生まれることは稀です。では、なぜ企業は新規事業以外の目的でビジコンを続けるのでしょうか。その大きな理由の一つが、2つ目のテーマである人材の発掘と育成です。こちらのテーマについては、もともと技術畑で関西電力に入社後、新規事業で実際に会社を立ち上げられた井上さんからお話を伺いたいと思います。
井上: 関西電力のビジコンは、人材育成が目的とは全く謳っていなくて、新規事業創出を目的としていますが、私自身は参加を通じて大きく成長できたと感じています。
私は技術系で入社して発電所に配属されて、オペレーションやメンテナンスなどを経験し、火力発電所の運転・保守・法令対応といった、リスクを避け安定を重視する業務に携わってきました。気軽な気持ちでアイデアコンテストに応募し、新規事業に触れることになりました。そこで驚いたのは、まずコミュニケーションの質の違いです。既存事業では「なぜ」「リスクは」と問われるのに対し、新規事業では「まずやってみよう」「失敗しても失うものはない」と肯定的に聞いてもらえました。
また、事業を論理的に検証し、スケーラビリティを説明する新たな経験もできました。そして、会社設立を通じて事業全体を俯瞰し、会計から営業、組織運営まで全てを自分で担う経験は、大企業の一担当者では得られない貴重なものでした。このように、社内ビジコンでの経験は、新規事業に限らず、論理的な説明力や前向きなコミュニケーションといった点で、私個人の成長に大きく寄与したと感じています。
田中:ありがとうございます。確かに火力発電所では失敗が許されませんが、新規事業はむしろリスクを取ることが推奨されるため、全く異なる世界ですね。ビジコンを通じて越境体験をされたと言えるかもしれませんね。
続いて、北瀬さん、これまでの経験から、人材育成や発掘においてビジコンが役立ったエピソードがあれば教えていただけますか?
北瀬:やはり人材発掘ですね。大企業では数万人の社員がいるため、埋もれた才能を見つけるのは困難です。日々の業務に集中する中で、新しいアイデアがあっても出せなかったり、BtoB企業でBtoCのアイデアが出ても受け皿がなかったりするケースがあります。ビジネスコンテストは、そうした隠れた才能を発掘する有効な仕組みです。本業で優秀なだけでなく、新しいことへ挑戦する意欲や情熱、伸びしろを持つ人材を発見できます。たとえアイデアが未熟でも、飛び込んできた勇気や行動力こそが重要です。こうした挑戦者には、優先的に研修機会を提供したり、社長直轄プロジェクトに抜擢するなど、健全なえこひいきをすることができます。やはり、タレント発掘機能としてはビジコンは非常に有効的だと思いますね。
田中:東急不動産の久保さんは如何でしょうか。

久保:おっしゃる通り、社内ビジコンは人材発掘に非常に有効だと感じますが、私たちの制度も7年目を迎え、ようやくその効果が表れてきたかなというのが正直なところです。これまでは、自ら情報を掴んでいける方々からの応募が中心でした。
しかし、ホールディングスとして取り組んでいる以上、グループ会社の皆様に幅広く届ける必要があると思っていましたが、多くの方が「私なんて」と自分ごととして捉えていただけず、制度が届いていないと感じました。そのため、人材発掘の機能を活かすには、まず間口を広げ、より多くの人に知ってもらうことが重要だと考えています。
田中:皆さんありがとうございます。社内ビジコンをうまく使うことで、既存事業では難しい色々な体験や機会を提供でき、人材の育成に繋がるということですね。また、ビジコンに参加すること自体が人材発掘の観点で重要であることが分かりました。
風土醸成の側面
田中:一方で、1人の方がビジコンを通じてすごく成長されたとしても、その方がその企業全体の価値を高めるということはかなり難しいのではないでしょうか。そこで、次のテーマである風土醸成に移りたいと思います。まずは久保さんからお話お伺いしてもよろしいでしょうか?
久保:社内ビジコンの目的として「風土醸成」を掲げる企業は多いですが、これってなかなか実現するのが難しいとも思っています。私たちの制度も7年目で、ようやく「風土醸成の観点では達成できたよね」との評価をいただきました。
ここまで何を工夫してきたかと言うと、まずは参加者を増やすことに注力しました。「毎年参加者がこれだけ増えています」と伝えることで、「毎年増え続けてるんだったら、これってちゃんと風土醸成できてるんだね」と評価していただけるというところですね。具体的には、応募前のエントリー期間にいろいろなイベントを実施し、イベント参加にはビジコンエントリーが必須というハードルをなくしました。それこそフィラメントさんにご協力していただいたりして、これまで新規事業を自分事と考えていなかった層にも興味を持ってもらい、「自分でもできるかも」と感じるきっかけを作っています。イベント参加者を増やすため、イベントでは「既存業務にも活かせる」という切り口で集客していて、実際100〜200人規模の増加に繋がりました。7年目でもマンネリ化しないよう、毎年制度をアップデートして告知することで、エントリー数が初期の2倍近く、応募案も約2倍に増加しています。
さらに、グループ会社の東急コミュニティー社から不動産の建設、維持、保全に関わる国家資格の合格を支援する学習アプリを提供する「株式会社リープロ |学習アプリ「LeaPro(Workschool))」が会社化したことで、グループ会社の方にも大きなインパクトを与えました。これにより、多くの社員が新規事業を「自分事」として捉えていただけるようになり、グループ会社からの応募も飛躍的に増え、風土醸成に大きく貢献できていると感じています。

田中:東急不動産の場合、エントリー期間のイベント参加のためにはアイデアがないといけないんでしょうか?
久保:アイデアがないと参加できないというものでは全くないです。イベントと言ってもオンラインかつ『お昼ごはんを食べながらちょっと聞いてみませんか』という感じなので、カメラオフで気軽に参加できます。でも、これが意外と届いていたりします。
田中:ビジコンを通じて企業風土醸成のためには継続的に実施することや間口を広げて社員一人ひとりに自分事化してもらうことが重要ということですね。大変参考になるご意見ありがとうございます。
最後に
田中:セッションの時間も短くなってきました。最後に一言ずつコメントを頂けたらと思います。
井上:ビジネスコンテストへの応募と起業を通じて、社会人としても個人としても価値観や経験が大きく変わったと思っています。もしビジコンがなければ、自分はこの挑戦をしていなかっただろうと思います。なので、こういった受け皿があることはすごく素晴らしいことで感謝しています。こういうサポートをしてくださるビジコン事務局の方々には、これからもぜひビジコンを続けていっていただけたらなと思います。
北瀬:現在、多くの企業でイノベーションへの挑戦が当たり前になり、そのための知見も蓄積され、挑戦しやすい環境が整ってきています。リスクのある事業への投資家も増えており、新規事業に挑むには非常に良い時期だと思っています。ヤマハとしては社内ビジコンを通じて、グローバルを視野に入れて、音やサウンドとなにかをかけ合わせる形で新たなチャレンジに踏み出したいと考えています。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお声がけください。
久保:新規事業の創出は非常に難しいことですが、事務局としては「なぜ良い案が出ないんだ」「全然成功してないじゃないか」といった批判を受けることも少なくありません。でも、その中で私がやりがいを感じるのは、起案者の方々が「成長できた」「やってよかった」と言ってくれる時です。そのために、私たちは事務局として、起案者のために少しでも汗をかき、彼らの満足度に直結するサポートを心がけています。本日いらっしゃっている事務局の立場の方もいらっしゃると思うのですが、事務局に共通する悩みが多くあるのではないかと感じています。ぜひ情報交換など通じて連携を深めていければ幸いです。
田中: 皆さん、本日はありがとうございました。今回のお話を通じて、やはり「人」の重要性と「継続すること」の大切さを改めて実感しました。久保さんのお話で、7年かけてようやく風土が変わってきたという評価があったのは、まさにその象徴だと思います。
会場の皆様も、これからも人材を育成し、企業価値を高めるために、社内ビジネスコンテストを有効活用してください。またいずれご一緒できる機会があれば幸いです。本日は誠にありがとうございました。
プロフィール
・井上 裕子(関西電力 イノベーション戦略グループ)
・北瀬 聖光(ヤマハ 執行役員 新規事業開発部長)
・久保 日乃(東急不動産ホールディングス グループCX・イノベーション推進部)
・モデレーター:田中 悠(フィラメント 取締役COO)