
2025年3月1日、東京・清澄白河にある「リトルトーキョー」にてフィラメントが主催したイベント「Beyond the Biz ビジネスを越境せよ #7「Business × 移住・二拠点生活」」が開催されました。コロナ禍を経て、生活スタイルが大きく変化した現代では、地方移住に対する感覚も大きく変わりました。「都市か地方か」という二者択一ではなく、都市と地方の両方で暮らし、それぞれの価値を取り入れながら豊かな体験を追求するライフスタイルが注目されています。今回は、特に「過疎ではなく適疎の町」として注目を集める北海道東川町で暮らすお三方をお迎えし、その魅力や気づきについてお話しいただきました。(文・写真/QUMZINE編集部・永井公成)
イベントに先立ち、東川町役場経済振興課の小林さんより、東川町の概要についてご説明いただきました。小林さんによれば、東川町は東京まで2時間半くらいで来れる距離にあり、美味しい地下水があるため北海道の179市町村の中で唯一「上水道のない町」として知られています。町は徒歩で歩ける範囲に様々な施設が集まるコンパクトシティであり、その外側には農地が広がって牧歌的な風景が広がります。町の東側には北海道で一番高い旭岳を含む国立公園が位置し、ウインタースポーツも盛んだそうです。

QUMZINEでは以前も東川町についてのイベントレポートを作成していますので、東川町の概要についてはこちらもご参照ください。
https://thefilament.jp/qumzine/8518
ここからはフィラメントの宮内さんが進行し、北海道東川町で暮らすスピーカーの3名に東川町の魅力や実体験についてお話しいただきます。まずは、スピーカーの皆さんに自己紹介をしていただきました。
成尾:
愛知県岡崎市の出身の成尾太希です。幼少期は父の仕事の関係でカナダやアメリカなど海外で暮らすことが多くありました。その後、大学進学を機に東京へ移り、卒業後はスイスの金融機関UBSに就職しました。13年間勤めた後に退職し、北海道の東川町へ移住しました。現在はRamps株式会社を立ち上げ、「東京一極集中」を是正することを目指し、人口の分散を促すサービスを手がけています。

梶:
私は三重県伊賀市の出身の梶恵理です。2008年に郵便局株式会社に入社し、郵便局の業務に携わってきましたが、2023年4月に北海道の東川町役場へ出向となりました。その半年後には慶應義塾大学の政策・メディア研究科の大学院に入学し、現在は日本郵便の職員、役場職員、そして大学院生という三つの立場で活動しています。

三浦:
千葉県館山市の出身の三浦慎二郎です。もともとサラリーマンをしていましたが、転勤で札幌に11年くらい住み、勤務していました。現在は地域おこし協力隊として活動しながら、「お菓子喫茶みうら」という焼き菓子とコーヒーの喫茶店を東川町で経営しています。そうしたお店を開きたいという夢を持ち、どこで実現するかを模索する中で、最終的に東川町に行き着きました。

ここからは、テーマディスカッションです。共通の質問について登壇者が答えていきます。
「3時間で移住を決めた」
宮内:
梶さんは二拠点生活、三浦さんは移住、成尾さんは東川町をメインに活動をされているそうです。そもそも東川町を知るきっかけって何だったのでしょうか?
梶:
社内で社会課題をビジネスで解決するために、プロフェッショナル人材を育てていくプロジェクトが始まり、会社だけでやっても限界があるので、慶應義塾大学SFC研究所の支援を受けながら進めることになりました。そして、支援いただいた先生の研究のフィールドからご提示いただいたうちの一つが東川町でした。
三浦:
札幌に住んでいた頃から、東川町についてはメディアで目にすることが多く、なんとなく興味を持っていました。コロナ禍のタイミングで姉家族と北海道旅行をした際に実際に訪れ、田園風景と美味しい水に心惹かれました。また、コロナ禍にもかかわらず、訪れたどのお店も活気があり、その様子を見て自然と自分たちも元気をもらっていました。知り合った方からの後押しもいただき、ここでなら自分たちの空気感に合うお店を開けるのではないかと考え、土地探しを始めました。田園や山の風景が見える場所で店を開きたいと考えていたため、理想の土地を見つけるまでに3年程度かかりました。
成尾:
前職ではずっと東京、シンガポール、香港といった大都市で勤務し、最後は香港に駐在していました。しかし、香港では新型コロナウイルスの影響が非常に深刻で、そこまでして人々がコンクリートの中で経済活動を続けなければならない状況に強い違和感を覚えました。そこで、一度地方に目を向けてみようと決意し、会社に休暇をもらい、沖縄から順に北上しながら各地を巡る計画を立てました。半年間かけて、できるだけ田舎の地域に焦点を当てながら旅を続け、その過程で「東川町」の名前を耳にすることが増えました。そして、東川町は北海道にあるため旅の最終目的地として訪れることになり、6ヶ月かけてようやくたどり着きました。実際に足を踏み入れてみると、たった3時間で移住を決断するほど強い魅力を感じました。東川町から多くを学びながら、日本全国にその良さを広げていきたいと考えています。
距離感の近さが東川町の魅力
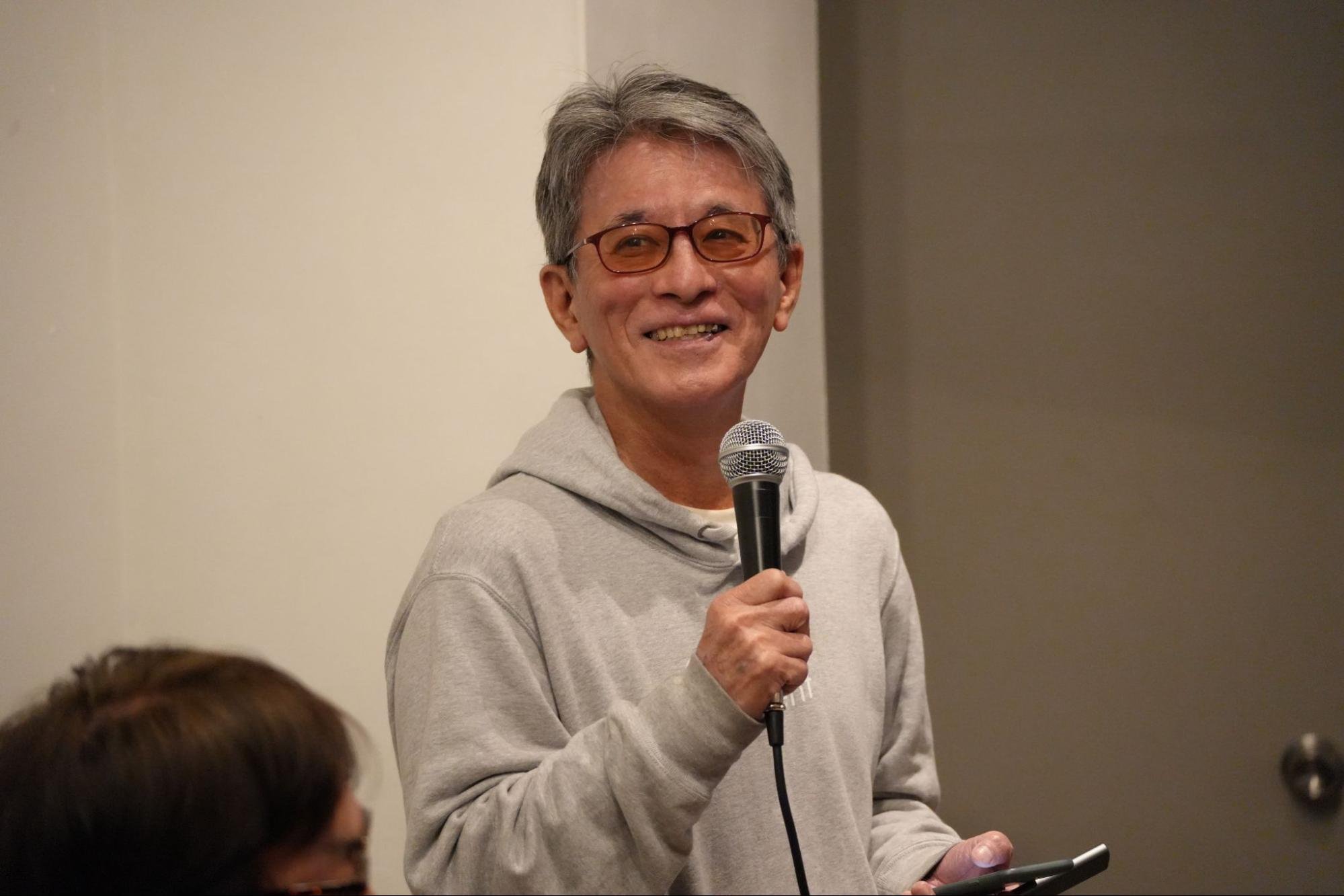
宮内:
東川町に住んでいて、皆さんに共有したいエピソードはありますでしょうか?
梶:
東川の人たちって、声をかけるとすぐに集まってくれるんです。私が移住して最初の年、仕事の一環で地域の中で郵便局をどう活用するかに悩んでいました。どうしていいのかわからず、とりあえず「郵便局の2階でカレーを作ってみたい」と思ったんです。そこで、「カレーを作るので、一緒に食べてくれる人、楽しい話をしてくれる人を募集します」と呼びかけたら、なんと20人くらい集まってくれたんですよね。こういう温かさが、東川の面白さだと思うんです。何かやろうとする人や頑張ろうとしている人に対して、みんなで応援する雰囲気がある。よそ者を受け入れて、「一緒に面白いことをしよう!」という寛容さが、この町には根付いていると感じます。
成尾:
東川町って、飲食店はそんなに多くないんですよね。特に夜に飲めるお店となると、3〜4軒くらいでしょうか。しかも、その数少ないお店に行くと、大体同じ顔ぶれに会うんです。そして面白いのが、カウンターに座ると、ほぼ確実に友達ができること。自然と会話が生まれて、気付けば仲良くなっているんですよね。例えば、この間、東川町にある飲食店のカウンターでたまたま隣に座った5人と仲良くなったんです。話しているうちに、みんな単身赴任で2拠点生活をしていることがわかった。驚いたのは、その5人、東京では同じビルで働いていたんですよ。でも、東京では一度もつながらなかった。こういう出会いが生まれるのが、東川町の魅力なんだと思います。東京ではまずありえない。
宮内:
僕としては、東京だとそういうのが少なすぎると感じているんですよね。たとえば大阪だと、隣に座った人と自然に会話が始まるんですよね。「それ、美味しそうやな」とか、ちょっとした一言がきっかけでつながる。でも、東京ではそういう経験ってほとんどないんです。
三浦:
東川町でお店を開いてみて驚いたのは、旭川や札幌からもこんなに人が来てくれるんだということでした。もともとは冬なんてお客さんがほとんど来ないんじゃないかと心配はしていたんです。だからネット販売など頑張らないと厳しいかなと考えていました。でも、実際には町のポテンシャルがすごく高くて、思った以上に多くの人が訪れてくれました。お客さんと話していると、「次はどこに行けばいいですか?」とか「東川町のおすすめは?」と聞かれることが多いんですが、紹介したい場所が本当にたくさんあるんです。結果的に、お客さんが「東川町ってめっちゃいいところじゃん!」と言って帰ってくれるんですよね。自分自身、まだ移住して1年も経っていないですが、こうやって町の良さを自慢できるのは誇らしいし、東川町が本当にいい場所だからこそだなと実感しています。

不便を感じることはない
宮内:
東川町に住まれていて、暮らしやすさの点ではどう思われますか?不便なところはありますか?
三浦:
去年の5月に移住したばかりなので、1年も経っていないんですが、今のところ不便さはあまり感じていません。雪の影響についても、もともと札幌に住んでいたので、北海道の生活自体には慣れていたこともあり、特に問題はなかったですね。ただ、最近「物価が高いな」と感じることが増えました。当初は「地方に行けば少し生活費を抑えながら暮らせるだろう」と安易に考えていたんですが、実際はそうでもないですね。移住に際してマンションを探していた時も、「今は新築しか空いていませんよ」と言われて、結果的に選んだ物件も想定より高くなりました。そういった点では、地方=生活コストが安いというイメージとのギャップはありました。
梶:
私自身、不便さをあまり感じていないのは、2拠点生活をしていることが大きいと思っています。
普段の生活に必要な日用品は、町内にスーパーが2つあるので特に困ることはありません。車で30分走れば旭川に大きな無印良品やユニクロもありますし、月に1〜2回は東京に行く機会もあるので、必要なものは東京で買えばいい。2拠点を活かしながら生活しているので、特に不便を感じることはないですね。
また、東京の人は「雪が降ると家にこもるもの」と思っているかもしれませんが、北海道では毎日のように雪が降るので、普通に車に乗りますし、外出も特に問題ありません。そういう意味でも、不便に感じることはあまりないですね。
成尾:
東川町は「最先端の田舎」という感じで、めちゃくちゃ暮らしやすいです。ただ、物価は高いかもしれません。不動産価格については逆転現象が起こっていて、北海道第二の都市である隣の旭川市より高いと思います。午前中にアパートの空室が出ると午後には埋まってしまって内見はできないくらい人が集まっている状況ですね。でも空港までも近いですし、出張で東京へ日帰りもできます。2拠点生活をしていて不便に思う点はゴミ出しですね。燃えるゴミが週1回なので、タイミングがずれると大変です。

東川町はこんな人におすすめ!
宮内:
最後に、東川町ってどんな人に向いている町と言えそうでしょうか?
梶:
東川町は、人生を楽しみたいと思っている人に向いている町だと思います。何かに挑戦したい人にとっては、それが許容される町だと感じます。東京で仕事をして、東川町ではゆっくりとした時間を楽しむ、そんな2拠点生活のスタイルも受け入れられるし、それぞれの人に合った楽しみ方ができる町なんですよね。「どんな人でも楽しめる」と言ってしまうとざっくりしすぎるかもしれませんが、少なくとも都会の生活に疲れたり、違うモードで暮らしたいと思ったりしている人には、ぜひおすすめしたい場所です。
三浦:
どんな人にも合うと思います。特に東川を楽しんでいる方の特徴としては、自分からいろいろな場所に出ていって、自主的にコミュニティに参加している方が多いような気がします。コミュニケーションが得意でないと感じている方も、住む場所を変えたら変わるということもありますし、もちろん得意にならないといけない訳でもない。私自身は大雪山連邦を眺めながら珈琲を淹れている時間に豊かさを感じます。新しいものを求めるのではなく今ここにあるものに気付いて十分満ちていくという感覚。人との時間や町の風景、日々の生活に価値を見出せる方におすすめしたいです。
成尾:
東川町には、ポジティブなエネルギーが流れていると感じます。住んでいる人たちが前向きで、そういう空気感が町全体に広がっているんですよね。だからこそ、そういうエネルギーを求めている人にはすごく合う場所だと思います。 また、自然に近く、山との距離が近いというのも大きな魅力です。例えば、東川町には「キャンモアスキービレッジ」がありますが、今やニセコの1日リフト券は1万円を超えるほどの価格になっていますよね。でも、東川町の町民はシーズン券が1万円。これは圧倒的にお得ですよね。他にも行政が運営している施設は非常に安く利用できるんです。お風呂は500円で利用できる施設もありますし、ジムは100円です。こうした環境のおかげで、生活コストを抑えながらも、充実した暮らしを送ることができます。
宮内:
古里さんは東川町を含めて多拠点で活躍されていますが、どう思われますか?
古里:
どんなタイプの人にも間口が広い町だと感じています。先ほど居酒屋の話が出ましたが、実は僕自身、引きこもりがちなタイプなんですよね。もともと外で飲んだり、人と会ったりするのがそんなに得意じゃなくて。東川町に滞在していても、ほとんど部屋にいることもあります。でも、それでも快適に過ごせるんです。地方に移住すると、「コミュニティに入らなきゃ」とか、「人間関係が密になるのが大変そう」と心配する人も多いかもしれません。でも、東川町はそのあたりの距離感がちょうどいい。僕みたいにあまり積極的に外に出ないタイプの人間でも、気兼ねなく暮らせます。移住者が多い町だからかもしれませんが、町の人もそれぞれのスタンスを理解してくれているような気がします。たとえば、役場に行っても普通にフレンドリーに話せるし、無理に「地元の人と馴染まなきゃ」と気負う必要もないんですよね。 だからこそ、それぞれのスタイルで、思い思いに東川町を楽しめる。本当に懐が深く、間口の広い町だと思います。

この後は、質疑応答のほか、「交流タイム」として移住者らとリアルな生活についての会話をすることで大いに盛り上がりました。
【スピーカー】

成尾 太希氏 Ramps株式会社 創業者兼代表取締役
1985年生まれ、愛知県岡崎市出身。幼少期をカナダとアメリカで過ごし、慶應義塾大学および大学院で情報工学を専攻。卒業後、UBSに入社し、シンガポールでデジタル変革を推進。日本では三井住友信託銀行とのウェルスマネジメント会社設立や野村総合研究所との証券決済業務の新事業立ち上げに従事。香港ではアジア13カ国を統括する管理部・CTO部のCOOとして経営全般を担い、同時にグローバルのAI戦略チームを率いた。 2022年、「人間のこれからの生き方」をテーマに、グローバル課題の解決は地方にあるという信念のもと、北海道東川町にRampsを設立。誰もが都市と地域の両方で暮らすスタイルを実現できるよう、生産性と豊かな暮らしの両立を目指している。
梶 恵理氏 地域起こし研究員/適疎推進課 適疎推進室 マネージャー 日本郵便株式会社 課長
三重県伊賀市出身。2008年に郵便局株式会社(現:日本郵便株式会社)に入社。ゆうちょ・かんぽを始めとする金融営業の企画、郵便・物流部門の法人営業人材の育成、広報ではインナーコミュニケーションやCIの業務に従事。2023年4月から、北海道東川町役場の適疎推進課に出向。人口減少を迎え、地域で生活に必要なサービスの集約化が推進されている日本において、生活関連サービスの最後の砦となりうる郵便局が、地域住民とサービス提供者(企業・自治体)の共創を促しながら、暮らしに必要なサービスをデザインし、生み出していくリビングラボの実践を構想。2023年9月に慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科修士課程入学。
三浦 慎二郎氏 地域起こし協力隊
千葉県館山市出身。大学を卒業後、広告代理店に就職。研修後の配属先として札幌に赴任。その後11年間は営業として、札幌の企業を中心に広報活動のサポートを行う。会社員をしながら休日はコーヒーショップに勤務。また、札幌の音楽フェスのスタッフとして稼働するなど、心豊かにいれる場所や経験を求めながら、会社以外のコミュニティを広げる。同時進行で、パティシエの姉夫婦と喫茶店の開業を計画。2020年旅行先として立ち寄った東川町の風景に憧れを抱き、土地探しをスタート。約3年後に希望の土地が見つかる。2024年5月に会社員を卒業し東川町へ移住。6月からは東川町の地域おこし協力隊員として従事しながら、店舗「お菓子喫茶みうら」の喫茶担当として珈琲の焙煎、抽出業務、空間作りを行っている。
【モデレーター】
古里 圭史 東川町産業振興ファイナンスアドバイザー
宮内 俊樹 フィラメント シニアコンサルタント
佐藤 啓一郎 フィラメント CXO
QUMZINEを運営するフィラメントの公式ホームページでは、新規事業の事例やノウハウを紹介しています。ぜひご覧ください!
https://thefilament.jp/know-how
