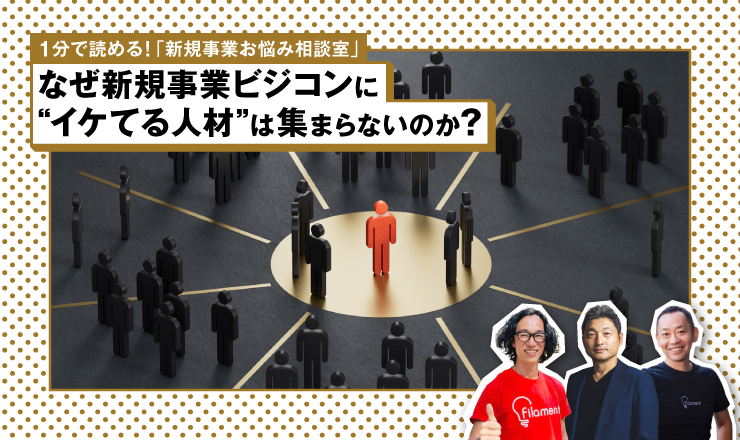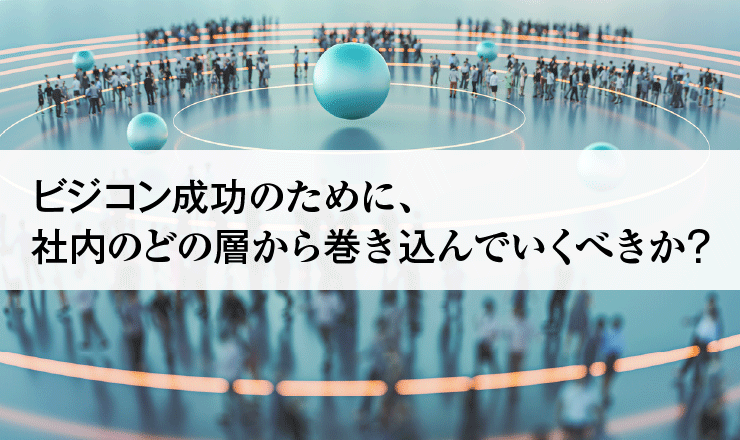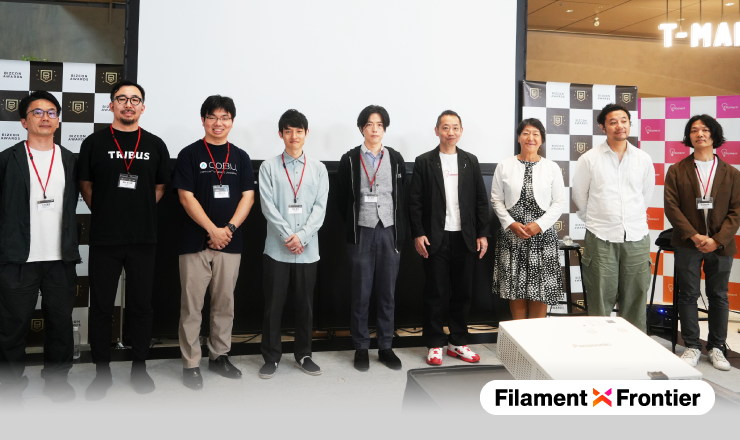新規事業開発研修プログラムを人材育成にも活用
伊藤:本セッションのテーマは「新規事業推進における体験学習の実践と効果」です。新規事業について考えるときは、どうやってどれだけのイノベーションを生んでいくのかという話になりがちですが、人材育成に着目するのはユニークですよね。まずは登壇者の皆さん、ご挨拶をお願いします。
羽室:NTTテクノクロスの羽室です。NTTテクノクロスは、NTTの研究所の研究開発の支援をして、そこで創出した新規技術や開発スキルを強みに、NTTグループの様々なサービスを提供するシステムの受託開発をしたり、自社製品・サービスを提供する役割の会社です。会社全体では様々な業界のお客様に対してビジネスをしていますが、私が所属する事業部はNTTグループの通信サービスの装置や運用システムの受託開発と、通信技術の研究所からの受託開発がメインのビジネスです。
私自身はは27年間NTTの研究所とNTTデータの研究開発部門に在籍し、5年前にNTTテクノクロスに移りました。NTTテクノクロスでは既存の受託ビジネスの顧客開拓や案件開拓を中心に取組んでいましたが、去年から新規事業開発の取り組みを始めています。

伊藤:順調に進んでいますか?
羽室:実はこれからなんです。去年の後半からフィラメントさんにお手伝いいただいていますが、今週末に新規事業開発プログラムのキックオフを行い、今年度末までフィラメントさんに人材育成と新規事業開発の伴走支援をしていただくことになっています。
伊藤:なるほど。続いてはJFEエンジニアリングの玉置さん、自己紹介をお願いします。
玉置:JFEエンジニアリングの玉置です。JFEときくと、製鉄のイメージが強いと思いますが、我々はエンジニアリング業を営んでいます。環境・エネルギー・社会インフラ分野を中心に、プラントやインフラの設計から建設、時には運営まで手がけています。私は新卒で入社し、人事部に7年所属した後、2年前に新規事業開発部門に異動してきました。今は新規事業創出プログラムの事務局を担当しています。
伊藤:順調ですか?
玉置:プログラム自体は5年前に始まったのですが、当初は応募ハードルが高く感じられるような制度設計になっていました。2年前から、制度自体をリニューアルしています。近年はプロモーションにも力をいれているので、プログラム知名度は上がってきたと思いますが、制度開始当初のイメージもまだ強く残っています。経営層や社員に新たな方針を理解してもらえるよう、奮闘中です。
伊藤:そんなお二人をサポートされているのがフィラメントの柿木原さんですね。
柿木原:フィラメントの柿木原です。現在、フィラメントとしてお二人のご所属する企業の新規事業推進および人材育成のご支援をさせていただいています。よろしくお願いいたします。
伊藤:柿木原さんから見てこの2社さんの共通点や相違点について教えていただけますか?
柿木原:まず共通点としては、、お二人とも日本を代表する大手企業グループに属しておられ、「新規事業の推進」や「新規事業人材の育成」がミッションとして担っていらっしゃることです。また、現在フィラメントとしてご一緒させていただいている担当者という点も共通していますね。一方で、相違点についてはバックグラウンドの違いがまず挙げられます。羽室さんは長年にわたり研究・技術開発の世界にいらっしゃった方で、、一方の玉置さんは人事を中心とした経歴をお持ちです。もう一つの大きな違いは、「新規事業推進」という同じ言葉を使っていても、その立場や会社におけるスコープが全く異なるという点です。例えば羽室さんは、グループ企業の一部門に所属し、既存の事業部門の中で新規事業を推進する立場にあります。一方、玉置さんは、JFEエンジニアリングの全社的な視点で制度設計や運営を取り組まれているという違いがあります。
伊藤:なるほど。現在の新規事業推進の体制についてもうちょっと教えていただけますか?
羽室:事務局が3人で、新規事業開発のプロジェクト以外にも事業部全体の人材育成なども担当しています。実際に新規事業に挑戦している社員は兼務で17人です。市場のリサーチやアイデア出しのフェーズから開始し、5チームに分かれて進めます。年度末までに事業企画を作り上げてピッチを行い、事業部長が審査して来年度に本格的に投資して事業化を進めるか否かの判断を行う予定です。
伊藤:全期間を合わせると10か月ほどになると思うんですが、どのように進めていくんですか?
羽室:前半5か月、後半5か月に分かれていて、前半は自分たちの組織のアセットやお客様のリサーチを行ってアイデア創出をする予定です。そして、想定した顧客課題やビジネス性を検証して事業計画を作り上げていくのが後半です。その間、フィラメントさんが隔週もしくは毎週メンタリングを行なって進めていきます。
伊藤:なるほど、玉置さんのところはどうですか?
玉置:私の所属している事業開発推進の部門は11人で、公募型のプログラムの事務局としては私と上司の2人です。公募は年1回サイクルで運営しています。今年は、5~6月の2か月を応募期間とし、書類審査を経て7月から活動開始、3月に社長·副社長によるピッチ審査を予定しています。応募件数は、23年度20件、24年度30件と推移しています。24年度にはようやく、経営層のピッチ審査を通過し専任化フェーズに移行するチームを輩出できました。
ビズビルダーで、受託ビジネスのマインドセットから転換
伊藤:それぞれのプログラムの目的や設計思想について教えていただけますか。
羽室:私たちの事業部は、これまで受託ビジネスが中心でしたが、技術部門のお客様が多いので、「こんなことをこの技術を使って実現してほしい」というお願いをされることが多かったんです。そのためお客様の課題を自分たちで探すという経験があまりありませんでした。ただ、今後受託ビジネスの成長に限界が見えている中で、顧客視点で課題を見つけて解決策を考える能力を組織でも個人でも持たないといけないというのが、今回の取り組みの一番大きな設計思想です。また、生成AIが進化してきていてコーディングなどのエンジニアの役割がAIに代替される可能性も出てきていますので、エンジニアが主体的にお客様の課題を発見して解決することができないとまずいという認識もあります。
伊藤:エンジニアなんだけど、ソフトウェアの設計をするという領域から外に出て、お客様の課題を設計するということですね。でも、今まで受託ビジネスをやってきた人が課題を見つけようとしてもなかなか難しいんじゃないかという感じを受けるんですけど、どうですか?
羽室:そうですね。現時点では、お客様の言っていることを正しく聞いて、課題やニーズを発見する経験が少ないことが問題だと考えていますので、今回のプログラムでそういったスキルやマインドセットを学ぶことできるようになるのではないかと思っています。
伊藤:経営陣のコミットはどんな感じですか?
羽室:会社全体としては受託ビジネスをベースラインとして考えつつも、全社で自社プロダクトを開発する取り組みに力を入れていく方針になっています。ただ私たちの事業部では長く受託ビジネスが中心だったので、「そう言われても」という感じでした。そこで事業部長やリーダ層とも議論して「社外の専門家の支援を仰ごう」と判断してフィラメントさんにお願いしました。
伊藤:スキルだけでなくマインドセットもしっかりインストールしていくということですね。同じことを玉置さんにもお伺いしたいです。目的や設計思想について教えてください。
玉置:NTTテクノクロスさんとは似ているところがあります。当社も入札に参加して受注して、プロジェクトを推進するという受注産業がベースにありますので、プロジェクトをきっちりこなすことは得意な社員が多い一方で、新たに顧客課題を発見して価値を提供することには伸びしろがあると思っています。新規事業創出プログラムをやっていても、正解を求めがちなところが垣間見えますが、そうではなくて顧客との対話を通じてゴールを作っていくやり方も浸透してほしいです。

伊藤:実際に取り組まれた中で効果を感じた研修の事例があれば教えていただけますか。
玉置:フィラメントさんと一緒に合宿型のアイデアソンを実施しました。もともとアイデアソンは3年ほど前からJFE商事というグループ会社と人材育成の一環としてやっています。。今回は特に顧客課題の発見ワークに重点を置いて設計いただきました。グループ会社と言えど全く違う業態なので、グループワークをしながらお互いの会社について知り、「世の中の課題をJFEグループのアセットで解決する」という視点でディスカッションを進めました。JFE商事は多くが営業人材ですが、当社からはエンジニアが多く参加し、”今まで使ったことのない頭の使い方だった”という感想を多くいただきました。
伊藤:なるほど。個々の人を見ると目がきらっとなる瞬間がある感じですか?
玉置:そうですね。新規事業開発プログラムで実際に顧客に出会い、ヒアリングを経験すると、発言が変わってきたりします。これまで設計や技術開発ばかりしてきたエンジニアが「顧客の声を聴かなきゃいけない」という発言をするようになると、嬉しく思いますね。
伊藤:プログラム前の段階で打ち上げ花火的にイベントをやって、その後何か月かかけてプログラムをやると発言が徐々に変わってくる。そういう人が毎年増えていったら嬉しい感じですね。羽室さんはいかがですか。
羽室:昨年度、新規事業開発のマインドセットから学びたい思ってフィラメントの「Biz Builder(ビズビルダー)」を私が所属するビジネスユニットの中で全員に受けてもらいました。すると、「受託ビジネスと新規事業開発はこんなに違うんだ」ということが学べて受講者の皆さんからとても好評でした。そこで、更に250人いる事業部全体に対して実施したところ、「こういうマインドセットじゃなきゃダメだよね」ということが幹部レベルまで共有できたと感じています。
伊藤:「Biz Builder」は、フィラメントさんが開発した新規事業を疑似体験できるボードゲーム研修ですね。
柿木原:はい。新規事業について語られるとき、よく「失敗から学ぶことが大切だ」と皆さん言うんですよね。でも既存事業って失敗したら怒られるじゃないですか。現実の業務ではそう簡単に“失敗させてもらえない”のが実情ですよね。その点、ビズビルダーは、失敗体験と成功体験を疑似的に体験できるところにあります。。羽室さんの会社では、新卒1年目の方から役員の方まで全員が参加されていたのが特長的でした。役職や年次に関係なく真剣に取り組みフラットに議論をしている様子を見てまさに新規事業に必要なカルチャーだと強く感じましたね。
伊藤:新規事業をやっていくときに経験や年齢や役職は関係ないですからね。そういうフラットな状況を作るというのがすごく大事なことなので、すごくいいですね。
社員の認知を得るために食堂でビラ配りも
伊藤:事務局や実施策について、社内の理解や支援を得るために皆さん日々苦労されていると思うんですけど、どういった工夫をされていますか?
羽室:昨年度事業部の全メンバーである250人が「Biz Builder」を受けた後、今年の新規事業開発プログラムを手上げで募集することになったんですが、10人も手上げがありました。その際、本業と兼務することになるので、「毎月〇時間は新規事業開発プログラムに費やすことを認めます。本業からその人が抜けた分はそれをサポートした周りの人たちのこともちゃんと評価するので快く送り出してください」と伝えました。あとは、募集時の説明会で角さんにモデレータをして頂いて事業部のリーダー層の皆さんにトークセッションをしてもらったのですが、事業部長始めリーダの皆さんが「失敗してもいいからチャレンジしろ」と言い続けたことが、参加者の皆さんを強く後押ししたようです。
伊藤:なるほど。トップの方がなんとなく「失敗してもオッケーだよ」というだけでは足りず、しっかりトークセッションとかをやって徹底することは大事ということですね。Biz Builderをやることで、レイヤーの上の人も下の人もフラットに失敗経験や共通言語を持つのって大きいですね。
柿木原:新規事業がまだ実際には生まれていない会社にとっては、新規事業を誰も知らないわけです。そうした中でボードゲーム型の研修というのは、新規事業に関する共通体験を生み出し、組織内に“共通言語”を生み出すことができます。これは単なる研修ではなく、組織文化の種をまく意味合いも大きいと思っています。
伊藤:玉置さんはいかがですか。
玉置:経営層を完全に味方にするというのは弊社にはまだ十分にはできていないことです。新規事業開発プログラムを盛り上げることそのものが、経営層の理解や共感に繋がると考え、まずは草の根活動を大事にしています。人事出身で社内に知り合いが多いほうなので、研修やイベントには個別に声掛けして仲間を増やそうと試みています。つい先日は、食堂でひたすらビラ配りしました。
柿木原:すごいですね。
玉置:社内の人間だと思わず素通りされることも多くて正直ちょっとつらかったですが(笑)、こういった地道な活動が結局どこかで実を結ぶのだと思います。
伊藤:ビラ配りでは「個人の力」を発揮されていますが、「関係性の力」も使った方がいいですね。「人事をやってたから社内のいろんな人とつながっている」ということです。案外ないがしろにされがちなんですけど、新規事業を作っていくときに個人の力だけではどうしようもなくて、知り合いとか、フィラメントさんとの関係とかそれを実際にパワーにしていくのはとても重要なのでぜひ活用されてください。

伊藤:最後に、プログラムのフォローアップやアルムナイについては何か取り組んでらっしゃいますか。
玉置:新規事業開発プログラムを実際に経験した社員とは、継続的に関係保持できるよう努めています。今年は“経験者登壇イベント+交流会”も開催しました。社員の中には、「自分にはできないかも」「アイデアが思いつかない」という方がまだ多く、新規事業に興味はあっても応募には至らない人が結構います。そういった方々には、事業推進パートナーとして通過チームに参画してもらえる可能性もあるので、まずは興味がある方の輪を広げることを試みています。
伊藤:「自分にはアイデアが思いつかないかも」という人もプールしておけば、そのマッチングに使えると。
玉置:はい。再チャレンジを促すアルムナイネットワークの活性化と、やってみたいけどまだそこまで踏み出せてない潜在社員のプールをいかに作っていくかというのが今年のテーマかなと思ってます。
伊藤:なるほど。羽室さんはいかがですか。
羽室:「なんちゃって」の取組みにせず、本当に来年度ビジネスを作って、市場に出していくつもりで事務局としては支援したいと思っています。今年度うまくいけば、来年度も同じようにできると思うので、ゆくゆくは3割くらいのエンジニアのマインドセットを変えていきたいですね。
伊藤:ありがとうございます。お二人ともぜひがんばってください!
プロフィール
・玉置 琴奈(JFEエンジニアリング βセンター)
・羽室 大介(NTTテクノクロス フューチャーネットワーク事業部)
・柿木原 明良(フィラメント 取締役CSO)
・モデレーター:伊藤 羊一(Musashino Valley 代表)