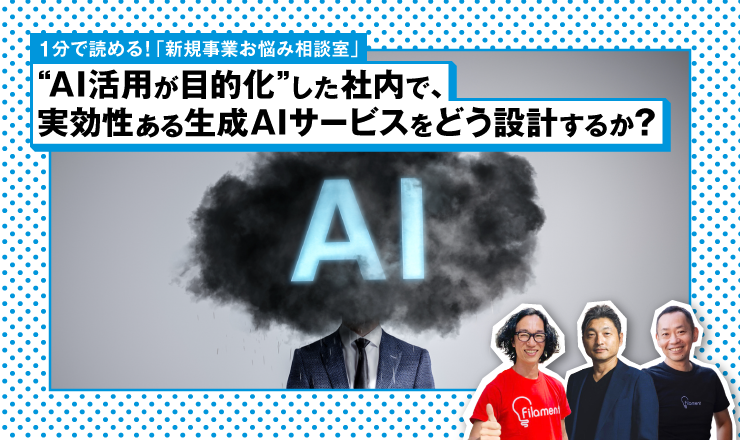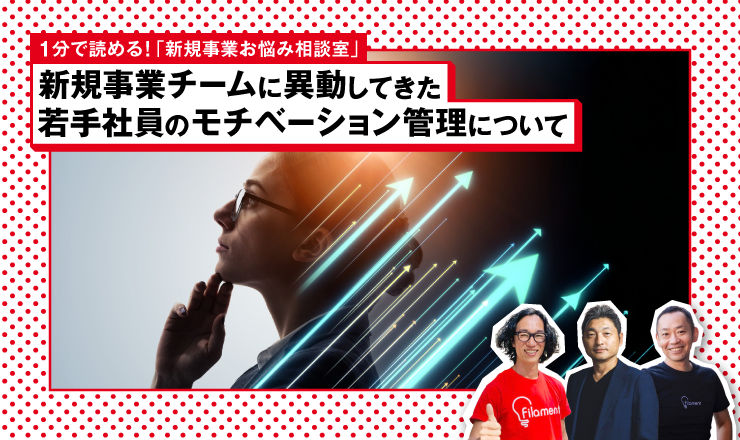フィラメント公式YouTubeチャンネルでは毎週水曜日に『新規事業お悩み相談室』を配信しています。この番組では、実際に新規事業に携わっている方々からお寄せいただいた質問やお悩みに、数々の新規事業の現場を見てきたスペシャリスト村上臣さん、グローバルなスタートアップ投資家として有名なリブライトパートナーズの蛯原健さん、そしてフィラメントCEOの角勝が相談員として回答しています。
本記事では、動画で配信している『新規事業お悩み相談室』を1分で読めるダイジェスト版としてお届けします。
今回いただいた相談は「“AI活用が目的化”した社内で、実効性ある生成AIサービスをどう設計するか?」です。
質問者:
大手メーカーグループのIT子会社・Dさん
相談の背景や理由:
大手メーカーグループのIT子会社で新規ソリューション開発を担当しています。最近、複数の事業部から「生成AIを組み込んだ新規サービスを何か提案しろ」と指示があり、ニーズも課題も曖昧なままPoCを回す日々が続いています。完成度や顧客視点よりも「AIをやっている実績」の見え方が優先され、意味の薄いPoCが量産されている状態です。社内では“AIを使うこと”自体が目的化し、テーマのように掲げられているだけで、実態が伴っていません。このような空気の中で、実効性ある生成AIサービスを設計・推進していくには、どこから手を打つべきでしょうか?
角:本日のご相談は大手メーカーグループのIT子会社Dさんから「”AIが目的化”した社内で、実効性ある生成AIサービスをどう設計するか?」についてです。なんとなく、2025年現在のこの世の中でこういう状況にある会社って、業界関係なくいろいろな会社でありそうだぞという気がしますね。こういう多くの皆さんがお悩みになっているであろうこの課題に対して、どうしましょうかね。まずは、グローバルな視点で見たときもこういう会社はあるのかというところも聞いてみたいので蛯原さんからお伺いしてもよろしいですか?
蛯原:ちょっと切なくなる質問ですよね。「AIの目的化」「ニーズや課題が曖昧なままのPoC」といったネガティブな言葉が並んでいることから、相当な不満や不安を抱えていらっしゃるのだろうと感じます。というところでちょっとリラックスしていただければなと思うところです。で、この手の悩みは当相談室でもよく聞かれますが、答えは1つです。まず、責任者つまり役員に直接会いに行き、もう一度しっかり話し合うこと。これは、新規事業の問題というより、社内のコミュニケーションの問題なのではないかと感じました。角さんから海外はどうなっているのかと言っていただきましたが、我々ファンドの出資者は日本の大企業さんも多いのでいろいろ聞きますけど、金融機関も事業会社もすでにAIの導入やPoCを始めています。
質問者の方は、「AIを使うこと自体が目的化している」とネガティブに捉えているようですが、私は経営陣がAIシフトという大きな時代の変化を真剣に捉え、危機感からそう発言しているのではないかと推測します。この溝は、コミュニケーションの問題である可能性が高いので、まずは経営陣としっかり話し合い、精神衛生を改善してから取り組んだ方が良いと思います。私たちが投資しているSaaS系のスタートアップは、ほぼ例外なくAIシフトを進めています。AIの活用はもはや当たり前になっていて、この流れに乗らなければ、やがて生き残れなくなります。もちろん、今すぐ全てをAIに置き換える必要はありませんが、新規事業としてAIに取り組むのは当然の流れです。悩むべきは、「やるべきか」ではなく「どうやるか」です。
角:そうですね。この質問からは、追い詰められている感じが伝わってくるので、まずはメンタルヘルス的な部分から整えていくアプローチもいいのかなと感じました。おそらく、新規事業部門ではない、たとえばマーケティング担当の役員などから「AIは見た目が大事だからやれ」といった指示を受けているのかも・・・というのはあくまで推測ですけど、このように同じことを言われても、誰が言うかによって受け取り方は変わりますよね。「この人が言うなら聞けるけど、あの人から言われると意固地になってしまう」といった、人間関係の複雑さが背景にあるのかもしれません。今井さんはどうでしょうか?
今井:そうですね。先ほど蛯原さんがおっしゃったことにも通じるのですが、まず1つの観点として、「ソリューション」とは何かを考える必要があります。ソリューションとは、何らかの課題を解決するものです。そう考えると、「生成AIを組み込んだ新規サービスを提案しろ」というオーダー自体が、すでにずれている可能性があって、まずは、事業部の「何を解決したいのか」という課題を言葉で明確にしてサービスを設計する必要があります。モバイルサイトやアプリのダウンロード数を指標にしても、それが何の課題解決にもならないのと同じです。何が重要業績評価指標(KGI)で、何が重要業績評価指標(KPI)なのかを、事業責任者としっかりすり合わせることが不可欠で、この「意味」をスポンサー側と共有しなければ、目的のないPoCが繰り返されてしまうことになると思います。
2つ目の観点として、今のモバイルの話にも通じるんですけど、歴史は繰り返されるという話です。インターネットが登場した時もそうでしたが、多くの企業が「生成AIを導入すること自体が競争優位性になる」と考えています。しかし、生成AIのような革新的な技術はいずれ誰でも使えるようになるため、導入すること自体は競争優位性にはなり得ません。たとえ一時的にアドバンテージを築けても、すぐに真似されてしまうからです。インターネットが普及し始めた頃、多くの企業がとりあえず「会社ポータル」を作りましたが、それだけでは何も起きませんでした。コストをかけたなら、ビジネスに直結するものを最初から設計する必要があったんです。生成AIも同じで、単に技術を使うのではなく目的を明確にした上で、ビジネスにどう組み込むかを設計することが重要です。過去の事例から学び、意味のないPoCで終わらせないためにも、この視点を持つことが、ご自身の精神衛生にとってもポジティブに働くのではないかと思います。
角:大手メーカーグループのIT子会社という点も気になっていました。一般的なIT企業とは少しカルチャーが違って、もしかすると、メーカーグループという性質上、外部との連携が少ないという環境なのかもしれないなと思いました。その結果、新しい情報が入りにくく、閉塞感が生まれて、精神的な負担が増しているのではないかなと。少し切羽詰まったような雰囲気も、そうした背景から来ているのかもと思っていたんですよね。
一般的なIT企業であれば、外部の生成AIサービスを積極的に使って、新しいアイデアや刺激を受けていると思うので、そうはならない環境にあるということ。また、親会社がメーカーであることから、親会社が喜ぶような、つまりシナジーのあるAIソリューションを作らなければいけない、というプレッシャーがあるのかもしれません。そうなると、顧客目線ではなく、親会社目線で物事を考えてしまい、「やらされている感」が強くなってしまいますよね。もし私の推測が正しければ、一度視野を広げてみることをお勧めします。親会社の顧客が何に困っているのか、どのようなAIソリューションがあれば喜んでもらえるのか、といったことを、「やらされている」という気持ちを忘れて、純粋な顧客目線で考えてみることで、仕事が俄然楽しくなるはずです。
もしかしたら「そんなことはわかってるよ」と思われたかもしれませんが、一度冷静になって、まずは精神的な健康を取り戻すことを考えてみてください。楽しく仕事をするという視点を、もう一度ご自身の中に育てていくのも良いかもしれません。ということで、大手メーカーグループのIT子会社Dさん、ぜひ参考にしていただければなと思います。
回答のまとめ
1.課題の本質とコミュニケーションの重要性:
・「AIが目的化している」という悩みは新規事業の問題というより社内コミュニケーションの問題である可能性が高い。
・経営陣の発言は危機感に基づくものであり、まずは役員層と直接対話し、意図や方向性を共有することが第一歩となる。
2.サービス設計の視点と歴史からの学び:
・AIサービスの設計は「何を解決したいのか」を明確にすることが出発点であり、PoCの乱発を避けるにはKGIやKPIを事業責任者と合意することが不可欠。
・インターネット普及期の「とりあえずポータルを作る」と同様に、AI導入も目的が曖昧なままでは競争優位性を築けない。技術を使うこと自体ではなく、ビジネスに直結させる設計が必要である。
今回ご紹介した内容は、以下のリンクから動画で視聴できます。