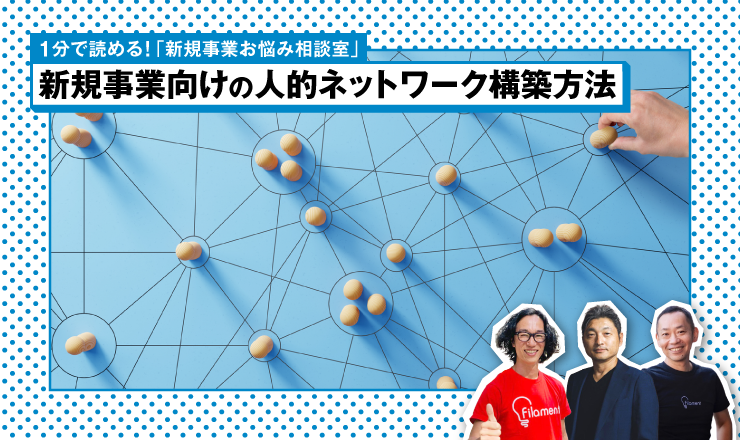フィラメント公式YouTubeチャンネルでは毎週水曜日に『新規事業お悩み相談室』を配信しています。この番組では、実際に新規事業に携わっている方々からお寄せいただいた質問やお悩みに、数々の新規事業の現場を見てきたスペシャリスト村上臣さん、グローバルなスタートアップ投資家として有名なリブライトパートナーズの蛯原健さん、そしてフィラメントCEOの角勝が相談員として回答しています。
本記事では、動画で配信している『新規事業お悩み相談室』を1分で読めるダイジェスト版としてお届けします。
今回いただいた相談は「「不」の解消が新規事業の必須条件なのか?」です。
質問者:
流通業界・Aさん
相談の背景や理由:
私は大企業で新規事業の立ち上げに携わっていますが、「不」の解消、つまり既存の課題や不満を解決することなしに新規事業は成功しないのでしょうか?私たちのチームは、市場に新しい価値を提供しようとしていますが、必ずしも明確な「不」を対象としているわけではありません。新規事業のアイデアを考える際、課題解決だけに焦点を当てるべきか、それとも他にも価値の提供方法があるのか、混乱しています。新しい視点やアプローチについてご助言をいただけないでしょうか?
角:本日のご相談は流通業界Aさんから「「不」の解消が新規事業の必須条件なのか?」についてです。不の解消って独特な言葉の使い方かもしれないですけど、リクルート系の新規事業の書籍を読むとこういったフレーズが出てきますね。おそらくこのあたりからの引用をされながらの質問なのかなと思います。
村上:あまり馴染みがないので、不の解消について、もうちょっと説明してもらってもいいですか?
角:僕も詳しいわけではありませんが、「不の解消」、つまり不利益や不便といった「不」のつくものを解決することをビジネスと定義している場合があります。世の中の様々な課題を解消することがビジネスである、という考え方ですね。
村上:なるほど。全ての事業は、何らかの新しい価値を提供し、その対価として料金をいただく、という点では同じです。それが課題の解決であれ、単に新しい価値を提供することであれ、顧客がそれを良いと感じれば、喜んでお金を払いますよね。そのため、事業を考える上で最も重要な問いは「顧客にどのような新しい価値を提供しているのか?」に尽きるんじゃないでしょうか。それは必ずしも不便さの解消とは限らない。この基本的な問いに立ち返れば、混乱は解消されるかもしれません。
角:多分、質問者の方はすごく勉強される方なんじゃないかなと思うんですよね。で、新規事業に関するいろんな本を読んでいくと、「新規事業とは不の解消である」って言い切っているものもあって、それを読んで混乱されたのかなと思いました。
村上:だとしたら、シンプルに事業を考えましょうに尽きるんじゃないかな。
角:そうですね。勉強熱心であるがゆえに生じている混乱なのかなという気もします。蛯原さんはいかがでしょうか?
蛯原:おっしゃる通り、英語圏では「プロブレム・ソリューション・アプローチ(課題解決型)」として、まず課題ありきで考えることがよくあります。ただ、それだけではなくて、純粋にポジティブな新しい価値やライフスタイルを提案することも成功に繋がります。たとえばiPhoneは、明確な課題があったわけではなく、新しい価値とライフスタイルを提示することで市場を創造しましたよね。したがって、「課題解決でなければならない」と結論を出す必要はありません。勉強熱心な方ほど、このアプローチにこだわりすぎてしまうことがありますが、実際には新しい価値の提供だけでも成功している事例はたくさんあります。
新しい定義や再定義も一つの方法です。たとえば、ユニクロの柳井さんが言ったとされる「服は部品である」という考え方は、ファッションを構成する「パーツ」と再定義することで、丈夫で長持ちするスタンダードな服を追求する事業に繋がりました。他にも、キャデラックが単なる移動手段ではなく「ステータス」を売ると再定義したように、提供価値を再定義することで成り立つ事業もあります。iPhoneが「新しいライフスタイル」を提案したように、「不の解消」だけでなく、様々なアプローチでビジネスは成り立ちます。
村上:今のユニクロの話で思い出したんですが、柳井さんの最大の気づきは、「ほとんどの人はファッションにそこまで興味がない」ということでした。ユニクロは、ファッション好きをターゲットにするのではなく、手頃な価格でシンプル、清潔感があり、安心して着られる服を求める大多数の人々に向き合ったんですよね。流行を追うような服は求められていないと見抜いたからこそ、それをグローバルに展開して成功した。これは新しい価値提供と言えますが、同時に、ユーザーが本当に求めているものにシンプルに向き合った結果でもあります。一方で、ハイブランドのように「着ていること自体がステータス」となる世界もあり、どちらが正しいというわけではなく、人それぞれです。
角:そうですよね。おっしゃる通り、ユニクロも今となっては「不の解消」になっている部分があると思います。たとえば、高齢者が「ちょうど良い服が見つからない」といった課題を解決していると捉えられますが、それはあくまで後付けの解釈でしょう。新規事業は、必ずしも最初から明確な「不の解消」を見つけていなくても成功します。キャデラックやロレックスがいい例です。ロレックスは、単に時間を知るための道具ではなく、「自慢したい」という人間の欲望を満たすために存在しているわけです。
村上:今となってはそうですよね。
角:そう、今となってはなんですよ。だから、後になって「実はこの欲求を解消しました」というパターンだっていっぱいあるので、それが絶対条件であると考えなくてもいいのかなという気がしますよね。
蛯原: そうですね。おそらく、この状況の一因として、私たちベンチャーキャピタルの責任もあると思います。様々なピッチイベントやアクセラレータープログラムで、「あなたが解決しようとしている課題(プロブレム)は何ですか?」と、徹底的に問い詰めるんです。もし答えに詰まると、「課題もないのに事業は成り立たない」と判断して、プロジェクトを却下してしまう。こうしたやり方が、もしかしたら世間の常識になってしまったのかもしれません。
角:なるほど。「カスタマー・プロブレム・フィット」とか、新規事業のステージを言う時の名称の中にもプロブレムって入ってきますもんね。
蛯原:たとえば、2007年にスティーブ・ジョブズがiPhoneを発表したとき、彼でなければ「何の問題を解決するんだ?」と言われたかもしれません。当時は多くの携帯情報端末があり、そのほとんどが失敗していたため、「お前は何の課題を解決しようとしているんだ?」と聞かれた可能性が高いんじゃないかな。
村上:iPhoneが出た当時、「日本ではキーボードがなくて、Suicaが使えない携帯は売れません!ワンセグもないじゃないか!」っていう話がありましたからね。
蛯原:Facebookも同様です。書籍にも書いたのですが、Facebookは現代人の「孤独」と「暇」という二大プロブレムを解決したと考えています。しかし、創業当初は単に「可愛い女の子の顔を比較する」といった、より個人の「ウォンツ(欲求)」を満たすものでした。このように、ユニクロやFacebookの例からもわかるように、事業が大成功を収めた後に「実はこの事業はこんな課題を解決していたんだ」と後から解釈されるケースは多いので、最初から「課題ありき」にこだわりすぎなくても良いと思います。
角:今回のこの質問については良い激論ができましたね。面白かったです。素晴らしい質問ありがとうございました!
回答のまとめ
1.価値提供の本質は「顧客に新しい価値を届けること」:
・多くの新規事業論やベンチャーキャピタルでは「顧客の課題(プロブレム)を解決すること」が重視される。そのため、「課題がなければ事業は成り立たない」という考えが常識化している側面がある。
・課題解決であれ、新しいライフスタイルやポジティブな価値提案であれ、顧客が「良い」と思えば対価を払う。事業を考えるときの核心は「顧客にどんな新しい価値を提供するのか?」という問いに尽きる。
2.「不の解消」は後付けで語られることも多い:
・成功後に「実はこの課題を解決していた」と振り返られるケースが多い。
・したがって、最初から課題解決に縛られる必要はない。
今回ご紹介した内容は、以下のリンクから動画で視聴できます。
本記事では要約をお伝えしましたが、テキスト化できなかった部分もありますので、回答のフルバージョンをぜひ動画でご覧ください。