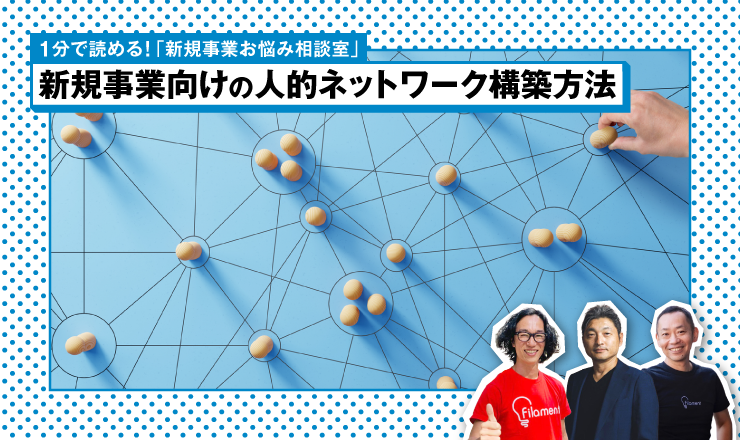フィラメント公式YouTubeチャンネル『新規事業お悩み相談室』では、実際に新規事業に携わっている方々からお寄せいただいた質問やお悩みに、数々の新規事業の現場を見てきたスペシャリスト村上臣さん、グローバルなスタートアップ投資家として有名なリブライトパートナーズの蛯原健さん、そしてフィラメントCEOの角勝が相談員として回答しています。
本記事では、動画で配信している『新規事業お悩み相談室』を1分で読めるダイジェスト版としてお届けします。
今回いただいた相談は「toB企業でtoC事業案を通すために事務局ができることは?」です。
質問者:
TIS株式会社 村上健太さん
相談の背景や理由:
弊社はSlerとしてtoB向け開発を主軸としていますが、社内ビジコンでtoC向け事業案が出ても検証継続が難しく進みにくい状況です。toC案を除外すると自由度が下がり応募も減る懸念があります。評価も難しい中、出島や子会社設立以外で、今の仕組みのまま事務局としてできることを知りたいです。
角:フィラメント新規事業お悩み相談室 公開収録三人目の方をお呼びしたいと思います。TIS株式会社、村上健太さんです。質問は「toB企業でtoC事業案を通すために事務局ができることは?」ですね。村上健太さん、相談内容の補足説明があればぜひお願いしたいです。
村上(健):我々TIS株式会社が行っている社内ビジコン「Be a Mover」では、アイデアに制限がなく、どんなアイデアでもいいよと謳っています。なので、応募されてくるアイデアにtoC向けのサービスというか、「自分あったらいいなと思う」アイデアがすごく多くて最終選考まで残るんです。そこから事業化に向けて頑張りますとなっても、実際には先に進み辛いと感じることがあります。
角:そうなんですよね。toB事業、toC事業にはそれぞれこういう特徴があるよといった教育などはされていたりしますか?それぞれの特性を御存知だったら、自然とどちらをやろうかなといった起点から考える気がするんですが、それがないから、自分の生活起点で思いつくアイデアをエントリーされているように見えます。
村上(健):応募者の皆さんの中にはエンジニアや営業職の方がいるのでtoBがどういうものかはある程度理解はしていらっしゃると思います。それでもやっぱり「自分がこうやりたい」「自分はこれが欲しい」っていうアイデアがどうしても多いというのが現状ですね。
角:なるほど。アイデアを事業化する際には、どのようなプロセスをたどるのかを明確にイメージできるよう、先にお伝えしておくべきかなと感じました。アイデア出しやコンテストの盛り上げだけでなく、コンテストから実際に新規事業が生まれるまでの「将来」をリアルに想像してもらうことが、まず重要だと思います。
そして、御社のメイン事業である「SIer事業」は一旦置いておき、「toB事業」と「toC事業」の比較をすると、このような違いが見えてくるのではないでしょうか。もちろん、相手が法人か一般ユーザーかという違いはありますが、それだけだと解像度が低いですよね。たとえば、予算規模はtoBの方が大きい傾向にありますし、顧客とのお付き合いもtoBの方が長くなる傾向があります。こういった違いは、もし比較表を作れば頭に思い浮かぶでしょう。
しかし、僕が思う一番の違いは、決済プロセス、つまり購入の意思決定プロセスの複雑さと、それに伴う人数の違いです。toB事業の方が意思決定が複雑で関わる人数も多くなりますが、toC事業は一人、あるいは少人数なのでシンプルです。この違いが、結果的に意思決定にかかるコストの大小につながります。そのため、toB事業では営業が主な売り方になりますし、toC事業では広告が主体になっていきます。このような事業の構造を、将来のことを考えずに、ただ思いつきでアイデアを出していないか、という問いかけをまずした方が良いのではないでしょうか。
村上(健):そうですね、確かに皆さんは自分の身近ないわゆる「半径5メートル」の範囲でアイデアを出す傾向があります。もう少し「顧客は誰か」「課題は何か」といった点を深く考えるように促すと、今度は尻込みしてしまい、結果的に応募数が減ってしまうんですよね。BtoBのような事業も増やしたい一方で、そうやって絞り込みすぎると応募件数が減ってしまうという、まさにジレンマに苛まれている状況です。
角:TISさんの場合だと、コミュニティをつくっているというのがあると思うんですけど、そこの中で教育をやっていくというのはどうなんでしょうか?
村上(健):コミュニティ内のメンターは新規事業の経験者が多いので、そういった方々から、たとえば「toC向けに見える事業でも、まずはどこかの法人に導入してから一般消費者向けに展開していくといいんじゃないか」といった、具体的な事業の進め方や戦略についてアドバイスできるかと思います。
角:SIerの仕事では営業部隊がエンジニアとは完全に切り離されていますよね。だから、エンジニアの人は営業も広告も経験したことがない。これが、おそらく新規事業を進める上で様々な食い違いが生じる原因なのではないかと僕は考えています。そのため、まずは営業や広告の具体的なイメージをしっかり持たせることが重要です。たとえば、「営業ってどんなことするの?」という問いに対して、漫画で読んだようなイメージしか持っていない人もいるかもしれません。そこから理解を深めていくと、状況が少し変わってくるのではないかと感じます。私ばかり話してもあれなので、村上さん、何か補足説明はありますか?
村上:今、応募の段階でどうされているかは分かりませんが、企画書と一緒に記入してもらうのが良いと思います。リーンキャンバスの簡易版のような形で、たとえばtoC向けであれば「ここはどうなりますか?」といった項目を最初に埋めてもらうんです。これによって、ユーザー数や、どういった調査結果が得られれば次に進むのか、といった点が明確になります。これが、まず最初にできることではないでしょうか。
あとは、やはり社内にtoC事業の経験者が基本的にいないわけですよね。だとすると、審査の段階や、あるいはメンタリングの際に、経験者にアドバイザーとして少し参加してもらうと良いかもしれません。多少時間を割いてもらい、経験者の声を取り入れるプロセスを入れることで、もう少しうまくいくのではないかと感じましたね。
村上(健):応募時点では、リーンキャンバスを任意で作成してもらうようにしています。ただ、その際にtoC向けのアイデアとして埋められてくる内容は、本当に生成AIに聞いて出てきたような、そのままの案が多いのが現状です。これでは、おそらく応募者が事業の全体像を本当には理解していないのだろうと感じていますので、今後はコミュニティ内でしっかりとその点を教えていきたいと思います。
村上:ただ、今の生成AIってすごくて、もはやリーンキャンバスとか言ってる場合じゃなくて、プロトタイプまで作れちゃいますよね。それこそ、toC向けのサービスを提案する人が来たなら、「いやいや、もうClaude Codeを使って動くプロトタイプを作って提出しなさい」というのを、もう最低限のハードルにしてしまってもいいくらいだと思います。
村上(健):エンジニアの会社なので、作ることに対しては皆さん楽しんで、むしろそっちに熱中しちゃう感じがあるので(笑)。一度作ってみてもらって反応を見てっていうところもありかもしれないですね。
角:ありがとうございます。TIS村上さん、ぜひ参考にしていただければと思います。皆さん、ありがとうございました!
回答のまとめ
1,コミュニティ内での教育強化:
・toB/toC事業特性や決済プロセス、営業・広告の役割を体系的に教育。
・経験者メンターが、toC向けアイデアの法人導入からの展開など、具体的な戦略をアドバイス。
2,応募段階と応募後の工夫:
・リーンキャンバス簡易版などで、事業の全体像を意識させる項目を応募時に記入してもらう。
・toC事業経験者を審査やメンタリングのアドバイザーとして招聘。
・生成AI等を用いた動くプロトタイプの提出を最低限のハードルとし、アイデアの具体性と熱量を高める。
今回ご紹介した内容は、以下のリンクから動画で視聴できます。