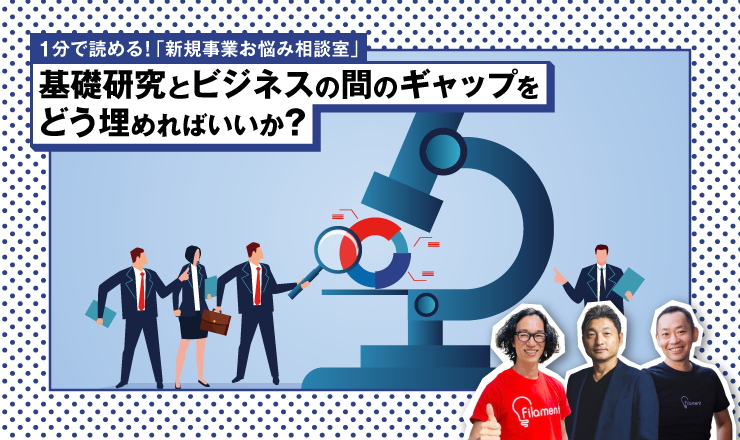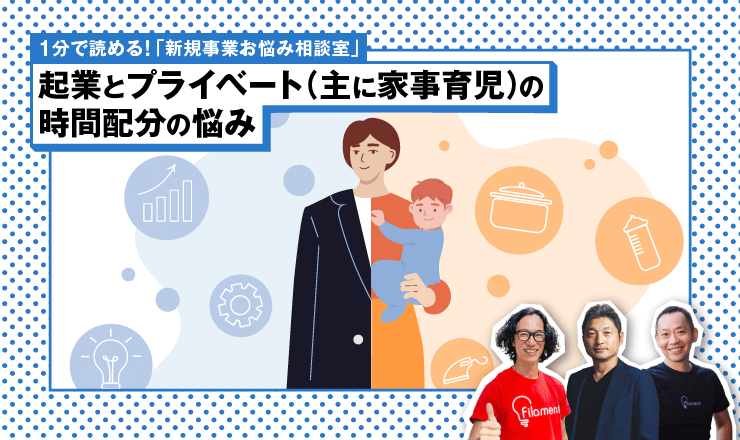フィラメント公式YouTubeチャンネルでは毎週水曜日に『新規事業お悩み相談室』を配信しています。この番組では、実際に新規事業に携わっている方々からお寄せいただいた質問やお悩みに、数々の新規事業の現場を見てきたスペシャリスト村上臣さん、グローバルなスタートアップ投資家として有名なリブライトパートナーズの蛯原健さん、そしてフィラメントCEOの角勝が相談員として回答しています。
本記事では、動画で配信している『新規事業お悩み相談室』を1分で読めるダイジェスト版としてお届けします。
今回いただいた相談は「基礎研究とビジネスの間のギャップをどう埋めればいいか」です。
質問者:
総合電機メーカーAさん
相談の背景や理由:
社内の経営層から「自社の研究部門での基礎研究は進んでいるが、まだ実装レベルに至っていないテーマで新しいビジネスの種を考えてほしい」と指示を受けています。(詳しく書けませんが、たとえば量子コンピュータのように技術的ポテンシャルは大きいものの、現状では汎用化に時間がかかり、応用先や顧客価値が具体的に描きにくい領域です。)そのため事業案を検討・提案しても「まだ早すぎる」「収益につながらない」と言われがちで、企画が進みません。こうした段階の技術をビジネス構想へと橋渡しするには、どのような切り口や検討プロセスが有効でしょうか。
角:本日のご相談は総合電機メーカーAさんから「基礎研究とビジネスの間のギャップをどう埋めればいいか」についてです。なかなか悩み深そうな感じしますね。こちらはテック系スタートアップの領域にもちょっと近い話なのかなという気がするので、蛯原さんからお伺いできればと思います。
蛯原:これは、いわゆるディープテック(基礎研究を基盤とする技術)に関するお悩みですね。経営層から非常に難易度の高い要求を突きつけられ、Aさんはさぞ大変だろうと思います。一般論として、基礎研究は、事業化までに数年〜10年、20年という長い時間(Jカーブ)を要し、失敗に終わるケースも多々あるものです。それを短期でビジネス化せよという要求は、基礎研究から応用研究、PoC、事業化というプロセスを飛び越せと言っているに等しいです。
この時間を短縮するには、オープンイノベーションによって外部の力を借りることが定石となります。具体的には、基礎研究の応用、つまりアプリケーションに強い外部企業を買収したり、提携したりして、時間を短縮する方法です。また、近い領域で既に事業を行っている企業に対し、そのテクノロジーを自社に組み込ませてもらうといった交渉をするというやり方があります。
さらに、もう一つの方法として、資金を投じて時間を買うことも考えられます。経営陣が無理な要求をしているのであれば、それに見合う予算を使って人とお金を投入してプロジェクトの期間を短縮する。資金と人員を投入して時間を圧縮するというのも一つの解決策となります。
角:なるほどです。
蛯原:たとえば新薬開発に置き換えてお話ししますと、AIを使って分子構造を探す新薬開発のように、何年もかかる基礎研究型の事業では、解決策として優秀なエンジニアを増やす**という方法があります。欧米勢がそうであるように、成果を出すには人への投資が不可欠です。したがって、経営層から無理な要求をされた場合、Aさんが取るべき戦略は主に2つです。1つ目は、「それだけの成果を望むなら、予算をください」と要求し、人員を増やして時間短縮を図る道。2つ目は、オープンイノベーションとして、買収や提携を活用し、外部の力を借りて時間を買うという道です。
角:オープンイノベーションの利用、なるほどなと思いました。あと、リソースをつぎ込むというのもたしかにその通りですね。僕も相談を見て、ちょっと理不尽すぎやしないかって思ったんですけど、「いやいや理不尽ですよ」と言い返すっていうところもありなんですかね?とにかく、お互いの溝を埋めるためには、強めのボールの投げ合いみたいなところもあるのかもしれなくて、蛯原さんの回答は非常に面白いというか、ちょっとスカッとする感じがありましたね。村上さんはいかがでしょうか?
村上:もう本当に心中お察しします。
角:心中お察しですよね。
村上:蛯原さんの回答は言い返すじゃなくて、お上品にご提案差し上げるというところですよね。
あとは、「力こそパワー」ですかね(笑)。とにかくリソースを投入して、AIもマシンパワーを買ってぶん回す。結局、確率論なので、AIの場合は物量を投入すれば当たる確率が多くなるというお話かと思います。で、この話を聞いていて、「新規事業をやれって言われて、いざ提案したら前例がないって言って断られて・・・」っていうのを思い出しました。
角:もうこれまで3回ぐらいそういった質問をいただいてますよね。
村上:そうそう。それを思い出したんですけど、僕はちょっと違うアングルでちょっとお答えすると、僕の所属していた昔の会社に研究所があったんですね。僕はそこで、研究と事業を繋ぐリエゾン(連絡調整)チームを見ていました。研究所は存在するものの、その研究をどうサービスに展開するかわからない、という課題を解決するチームです。ここで最も有効だったのは、研究のバックグラウンドを持ちつつ、事業経験もある人材を配置することでした。この人材は、研究者と共通言語で話せ、論文の内容まで理解できる一方で、事業経験を活かして研究内容を「翻訳」します。
研究者は自分の研究領域には詳しいものの、事業部門との会話が苦手なため、論文の興奮ポイントばかりを語りがちです。これでは事業側には遠い話に聞こえてしまいます。しかし、リエゾンの人が「この技術を使えば、こういう顧客の課題が解決できるかもしれません」といった具合に噛み砕いて説明できると、感度の高い事業側の人から「それ、うちの部門で使えるんじゃないか」という反応が返ってきて、PoCが始まることがあります。
たとえば、量子コンピューターが何なのか原理は分からなくても、「最適化や経路探索を現状より圧倒的に速くできる」と噛み砕けば、事業部門は「それなら、うちのお客さんが困っているこの課題が解決できるかもしれない」と気づけます。このように、リエゾンの役割を担う人材を採用するか、社内で専用の部門を作ることが、1つの解決策になると思います。
角:たしかにそうですね。研究所の研究テーマという視点からだけの話だと、ビジネス上こういう価値がありますよといったことが出てこないというか、研究とビジネスの間にある溝が埋まらないということですよね。
村上:そういうことですね。結局のところ、使ってくれる人の課題解決から入らないと、どんな技術もやっぱり役に立たないので。
角:なかなか難しいことを言われているということは、多分ご本人も、おそらく言ってる側の上司もわかっていて、でもその中で、Aさんがどういう切り口で、あるいはどういう方と知の融合を進めていくのかということを望まれているのかもしれないなとも思います。ということで、総合電機メーカーAさん、ぜひ参考にしていただければと思います。
回答のまとめ
1,ディープテックの時間軸と経営層の要求:
・基礎研究は事業化までに長期の時間(Jカーブ)を要し、失敗のリスクも高い。それを短期間で成果にせよという要求は現実的ではなく、経営層と研究現場の間に大きなギャップが生じやすい。
・短縮策としては、外部企業との提携や買収によるオープンイノベーション、あるいは人員と資金を大胆に投入して時間を買う方法がある。
2,研究と事業をつなぐ「翻訳者」の重要性:
・研究者は論文ベースの説明に偏りがちで、事業部門には価値が伝わりにくい。その溝を埋めるのが、研究知識と事業経験を兼ね備えたリエゾン人材の役割である。
・技術を顧客課題に結びつけて噛み砕くことで、事業部門の理解を促し、PoCや事業化のきっかけを生み出す。
今回ご紹介した内容は、以下のリンクから動画で視聴できます。