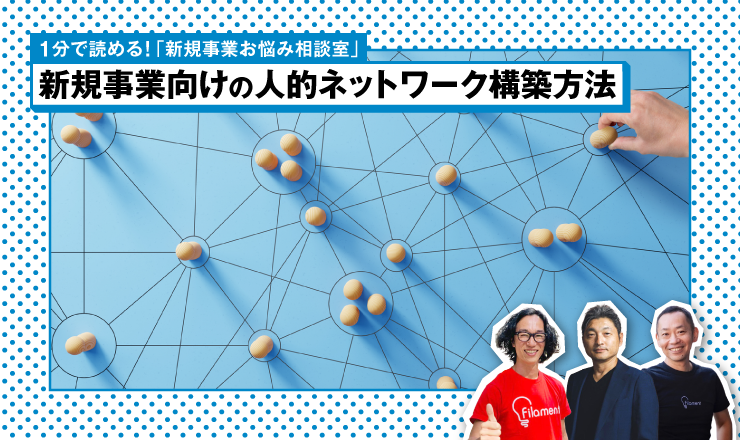フィラメント公式YouTubeチャンネルでは毎週水曜日に『新規事業お悩み相談室』を配信しています。この番組では、実際に新規事業に携わっている方々からお寄せいただいた質問やお悩みに、数々の新規事業の現場を見てきたスペシャリスト村上臣さん、グローバルなスタートアップ投資家として有名なリブライトパートナーズの蛯原健さん、そしてフィラメントCEOの角勝が相談員として回答しています。
本記事では、動画で配信している『新規事業お悩み相談室』を1分で読めるダイジェスト版としてお届けします。
今回いただいた相談は「ゼロイチをやめるべきか、踏みとどまるべきか」です。
質問者:
Sler業界・Cさん
相談の背景や理由:
SIerの新規事業開発チームを執行役員として統括しています。受託開発が主力の当社ですが、将来を見据えて自社サービスをゼロから立ち上げる取り組みを進めてきました。3年ほど仮説検証とPoCを重ね、一定のニーズは掴んだものの、収益化にはまだ時間がかかりそうです。最近では、「既存顧客向けの拡張サービスに振った方が確実」「商談化しやすい事業に絞るべき」といった声が経営層からも出ており、ゼロイチ案件に対する期待値が下がっているのを感じます。リソースをかける価値があるのか、自分の判断で撤退すべきか、迷っています。撤退と継続の線引きについて、見極めの視点をいただければと思います。
角:今回のご相談はSler業界 Cさんから「ゼロイチをやめるべきか、踏みとどまるべきか」についてです。撤退の話は過去の新規事業お悩み相談室でも何回か登場していますね。まずは、蛯原さんはいかがでしょうか?
蛯原:どういうオケージョンで、3年間の仮説検証(PoC)フェーズを過ごしたのかなと思いましたね。
角:SIerさんなので、割とちょっと長めに見ちゃってるのかもしれないですけどね。
蛯原:なるほど。とはいえ、ご質問は角さんが言われたように、この相談室で何回も出てきた撤退問題ですね。で、撤退問題についてどうしたらいいかと。そこで私がいつも投げかける問いは、「もし今この事業をやっていなかったとしたら、今からでもやりたいか?」というものです。質問文を拝見するに、おそらくCさんご自身は「イエス」と答えたい。しかし、組織としては「ノー」なので、自信を持って言い切れないというのが本質的な悩みではないでしょうか。
この問題を解決するには、事業計画の確度を高めるしかありません。「3年もかけたのだから、今さら撤退できない」というサンクコスト(埋没費用)があるようですが、撤退判断においては、このサンクコストは一切考慮すべきではありません。むしろ、「あと6ヶ月で、実際に顧客を2〜3社連れてくる」「プロダクトを動かすのが難しければ、Excelや紙でもいいからサービスを走らせてみる」など、徹底的に実現可能性を高めてください。そうして、ご自身の心の中にある「イエス」を、他者に対しても堂々と主張できるレベルまで磨き上げることが必要です。
角:なるほど。
蛯原:また、もう一つの冷徹な答えとして、撤退判断はマイルストーン戦略に沿って行うのが一般的です。「PoCまで」あるいは「1年経ったら」とそれぞれマイルストーンを設けて、そのマイルストーンに到達してなかったらシビアに切るというようなことを最初から決めて淡々とやる。マイルストーンがないのであれば今からでも遅くないので作って、あと6ヶ月で何ができなかったらやめるかを判断していくということかなと思います。
角:これまでの相談者とは異なり、執行役員という立場にある点が特殊ですね。これまでは「事業を辞めさせられそうだけど、どうしたらいいか」といった相談が多かったのですが、今回はご自身で撤退判断を下さなければならないという、責任の重さからくる葛藤があるのでしょう。ただ、どんな役職であっても、最終的には「今からでもこの事業をやりたいか」という問いを、自分自身に投げかけるしかないのだと、お話を聞いて改めて感じました。今井さんはいかがでしょうか?
今井:そうですね。まず私が相談者さんの立場なら、経営層と一度しっかり話し合います。「既存顧客向けの拡張サービス」や「商談化しやすい事業」を求めるのであれば、それは新規事業ではなく既存事業の延長です。本当に新規事業をやる気があるのか、経営層が考える「新規事業」の定義や期待を改めて確認し、目線を合わせることが重要です。このすり合わせができていないと、ずるずるとプロジェクトが続き、撤退や継続の判断が曖昧になり、後から「言った言わない」の水掛け論になりかねません。
次に、撤退基準はドライに設定すべきです。感情的なサンクコストに引っ張られないよう、客観的なチェックポイント(例:10点満点で何点以上なら継続、といった基準)を設けるのが効果的です。情に流されて決断を先延ばしにすると、結局は誰も幸せにならない状況を招くことになります。
角:SIer業界の新規事業には、特有の難しさがありますよね。受託ビジネスの特性上、案件を受けた時点で利益が確定するため、あとはコストをいかに削るかが重要となります。そのため、コスト増や不確実性に対して極端に厳しい組織文化になりがちです。この文化が、新しいサービスを生み出す際の障害となることがあって、事業として成立しそうなアイデアがそもそも生まれにくく、良いアイデアが出たとしても、そこに固執してしまいがちになります。サンクコスト(埋没費用)が発生しやすい環境と言えると思います。そのため、3年もの時間がかかっているのかもしれませんね。
3年という期間が経ったのに事業を辞められず、収益化にまだ時間がかかりそうという、典型的なサンクコストに囚われている状態だと感じます。この感覚は、相談者さん自身も薄々感じているのではないでしょうか。SIer業界は、不安から新規事業に手を出そうとするものの、受託開発の文化に引きずられ、なかなかうまくいかないという二律背反を抱えがちです。しかし、AIによる自動コーディングが現実のものとなっている今、「〇〇年の崖」といった昔からの課題とはレベルが違います。この危機的な状況を乗り越えるためには、今の事業に固執するのではなく、一度諦めてでも、改めて新規事業に真剣に取り組むべきだと思います。今のプロジェクトを諦めるのではなく、新規事業を改めてスタートさせる。その意思を経営層としっかり共有し、本当の意味で再出発することが、生き残るための道ではないでしょうか。
蛯原:私も質問を拝見しながら思いました。「ゼロイチ案件に対する期待値が下がっているのを感じてる」と書いてらっしゃるんですが、そうじゃなくて、この事業案がイマイチだと思ってる可能性が結構あるんじゃないですかね?日本企業は諸外国の企業に比べてはっきり言わない場合が多いので、イマイチだと思っていても言い出しづらいんじゃないですかね。
角:そうなんですよね。ちょっと冷静に俯瞰的に、ご自身が置かれている状況を見直してみるのもいいのかなと思いました。SIer業界のCさん、ぜひご参考にしていただければと思います。
回答のまとめ
1.判断の基準は「今からでもやりたいか」と明確なマイルストーン:
・新規事業を続けるかどうかは、サンクコストに囚われず「もし今この事業をやっていなかったとしても、今から始めたいと思えるか」という問いに立ち返ることが重要
・その上で、半年以内に顧客を獲得する、紙やExcelでもサービスを動かしてみるといった短期的な検証マイルストーンを設定し、客観的に実行可能性を示せるかどうかで判断する
2.SIer業界特有の文化と「事業案そのもの」の再評価:
・受託開発を前提とするSIer業界では、不確実性に極端に厳しく、結果としてアイデアに固執しサンクコストが膨らみやすいという文化的な難しさがある。しかし、AIによる自動化などの変化に対応するためには、一度諦めてでも新しい挑戦を始める覚悟が求められる
・組織内で期待値が下がっているのは「事業案自体が魅力に欠ける」と見られている可能性もあるため、冷静に案そのものの価値を見直すことも必要
今回ご紹介した内容は、以下のリンクから動画で視聴できます。