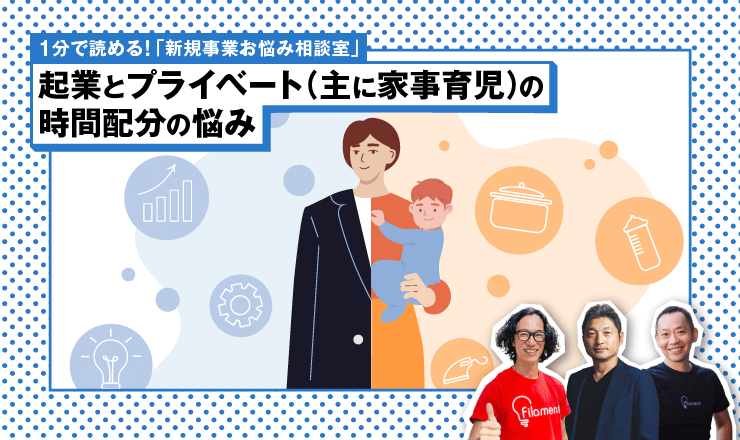フィラメント公式YouTubeチャンネル『新規事業お悩み相談室』では、実際に新規事業に携わっている方々からお寄せいただいた質問やお悩みに、数々の新規事業の現場を見てきたスペシャリスト村上臣さん、グローバルなスタートアップ投資家として有名なリブライトパートナーズの蛯原健さん、そしてフィラメントCEOの角勝が相談員として回答しています。
本記事では、動画で配信している『新規事業お悩み相談室』を1分で読めるダイジェスト版としてお届けします。
今回いただいた相談は「ゼロから新規事業のテーマを選ぶ時の探し方」です。
質問者:
通信業界 Aさん
相談の背景や理由:
大手企業の新規事業担当として、自身の原体験に基づいて選んだテーマについてピボットするよう指示されました。(選択した市場はレッドオーシャンであり、さらに自社のリソースを活用するのが難しいため) 現在、この状況からどのように進めていくべきか頭を抱えています。
角:本日のご相談は通信業界Aさんから「ゼロから新規事業のテーマを選ぶ時の探し方」についてです。まずは村上さんからお伺いしてよろしいでしょうか?
村上:本当に頭を抱えていらっしゃる状況だと思います。話を進めていたはずなのに、「なぜ今になってフィードバックが」というお気持ちですよね。これは大企業の新規事業では「あるある」です。まず、どれくらいの規模で、どのようなテーマの新規事業をやるのかという、事前の擦り合わせが非常に重要です。上の方と会話はされていたと思いますが、ご自身の現体験で選んだテーマが、会社の求める規模感と合っていなかったのかもしれません。会社には、「TAM(獲得可能な最大市場規模)が〇桁足りない」とか「5年後に10億、あるいは100億の利益が必要」といった、セットアップ(目標)があるはずです。これらを最初に上層部としっかり握り、かつメールなどで記録を残すといった自衛的な保険も必要になってきます。
今回フィードバックが来たのは仕方がないとして、これを機に期待値の握り直しをすべきです。「レッドオーシャン」や「シナジーがない」と言われた詳細について、「なぜダメなのか」という理由を考えた上で「会社が期待するテーマや規模はどこにあるのか」を明確にするのです。自社のリソースを活用するという点については、たとえば、営業部門のように汎用性のあるリソースを活用するのか、あるいは既存サービスとの兼ね合いでシナジーがないと言われているのかといった詳細を詰める必要があります。まず、わからなければ、アイデアを100個くらい出してみて、「これですか?これですか?」と、上司の方がはっきり言語化できるように仕向けるのが一番良いでしょう。そして最終的には、「何年後にどれぐらいの規模のビジネスになっていれば、うちの会社として良しと言えるのか」というところを、改めて当たりをつけておくことです。これをやってから詳細を詰めていかないと、この立場は「自分のやりたいことをやる」というセットアップではないと思うので、そこが少し足りなかったのではないかと思います。
角:相談者さんの頭を抱えている感じには、「本当はこれをやりたかったんだけど、ダメって言われちゃった」みたいな、うまく消化できないような雰囲気もちょっと感じられるかなと思いますけども。
村上:気持ちはすごくよくわかります。ただ、会社が求めてることに応えるっていうのは会社員の宿命ですので、そこは割り切ってやられて、そうじゃないものは副業などの形で別途追っていくのがいいんじゃないかなと思います。
角:さすが『稼ぎ方2.0』の著者ですね。蛯原さんはいかがでしょうか?
蛯原:これはほとんど村上さんがおっしゃったことに尽きますよね。質問文を読み解くと、「自社リソースを活用するのが難しいからダメ」と言われたということは、そもそも自社リソースの活用がマストだという要件定義ができていなかったということですよね。これがまず要件の1つです。もう1つは、「選択した市場がレッドオーシャンである」という点です。これは、「世の中に全くない、新しいタイプのものを作れ」か「同じ市場に見えてもアプローチをずらせばいい」かのどちらかだと思います。
たとえば、スタートアップの例で多いのは、既存プレイヤーがエンタープライズつまり大企業向けに集中しているのに対して、「うちはSME(中小企業)向けをやります」というように、市場のサブセグメントを変えるパターンです。同じ市場に見えても、サブセグメントを変える、あるいはアプローチを少しずらしてあげるなら良いのか、それともその市場自体が何らかの理由で嫌なのか。いずれにせよ、先ほど村上さんがおっしゃったように、経営の意思として「これとこれとこれの要件がないとダメ」という定義があるなら、あらかじめそれをもう一度定義し直すべきです。その結果、残念ながらゼロベースでやり直すしかないという結論なら、会社なので仕方がないと割り切るしかない。ただ、意外と少しずらせばいけるという感触が得られるなら、それで進めていきましょう。私はこのように読み解きました。
角:なるほど。お二人の話を聞きながら思ったんですけど、選択した市場がレッドオーシャンで競合がいっぱいいるってことですよね。「自社のリソースを活用するのが難しい」というのは、結局「武器がありません」ということだと思います。つまり、「武器がない状態で敵が多いレッドオーシャンに飛び込むのは勝ち目がない」ということを言われてしまったのだと理解しました。また、ご自身の原体験で選んだという点から、これはボトムアップで進められた企画だと読み解いたんですが、先ほどのレッドオーシャンの理由を含めこのままでは時間ばかり浪費してしまい誰にとっても良くないということを上司の方は伝えたかったのだと思います。
まず、Aさんはこのフィードバックを一度受け止めることから始めるということが必要ではないでしょうか。そして、「それはもう仕方がないことなんだ」という心の整理をした上で、先ほどお二人がおっしゃったような、ターゲットをずらすといった方向性を考えていくのが、ご自身のためにもなると思います。その上で、ゼロから新規事業のテーマを選ぶ際の探し方として、今回OKが出なかったのは、「レッドオーシャンであること」と「リソースの活用が難しいこと」の2つのネガティブな要素が重なってしまったことが原因だと思います。どちらか1つだけなら許容された可能性もあると思うので、「どちらか1つだけなら良いですか?」というのを、上司の方に確認してみて、村上さんがおっしゃっていたように上司の方としっかり握って進めていかれるというのが良いのかなと思いました。ということで、通信業界Aさん、参考にしていただければと思います。
回答のまとめ
1,新規事業は「上層部の期待値の明確化」から始まる:
・事業規模・目標利益・リソース活用の方針など、経営側が暗黙に持つ条件を初期段階で明確にしておくことが不可欠。
・「なぜダメなのか」「何を求めているのか」を具体的に聞き出し、言語化できる形で合意を取る。
・合意内容は口頭で終わらせず、記録として残し、後々の軸をブレさせないための“保険”として活用する。
2,「市場の選び方」と「自社リソース」の整合を取る:
・「レッドオーシャン」と言われた場合は、ターゲット層やアプローチを少しずらすなど、差別化の余地を探る。
・「自社リソースを活用できない」と指摘された場合、その前提条件を再定義し、使える強みを再整理する。
・両方が満たせない場合は、テーマをゼロベースで見直す覚悟も必要。どちらか一方だけを妥協できるか、上司と再確認する。
3,「個人の想い」と「組織の要件」を分けて整理する:
・原体験から生まれたテーマでも、組織の求める条件に合わなければ通らないことを受け入れる。
・自分がやりたいテーマは副業や個人プロジェクトとして追うなど、場を分けて考える。
・組織の中では「会社の目的を叶える事業を設計する」視点に切り替えることで、次のステップが見えてくる。
今回ご紹介した内容は、以下のリンクから動画で視聴できます。