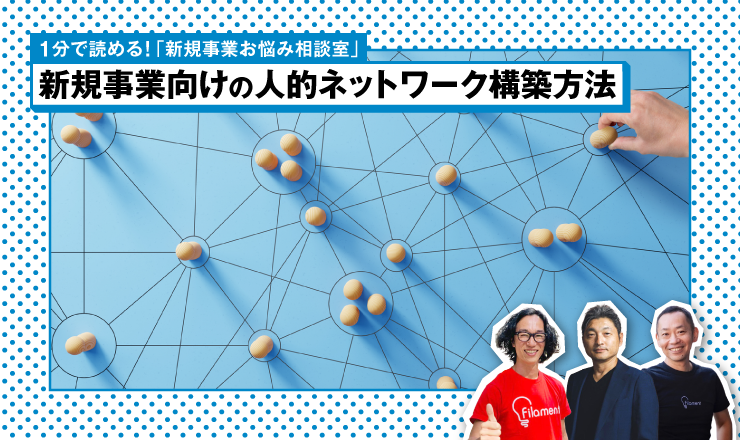フィラメント公式YouTubeチャンネルでは毎週水曜日に『新規事業お悩み相談室』を配信しています。この番組では、実際に新規事業に携わっている方々からお寄せいただいた質問やお悩みに、数々の新規事業の現場を見てきたスペシャリスト村上臣さん、グローバルなスタートアップ投資家として有名なリブライトパートナーズの蛯原健さん、そしてフィラメントCEOの角勝が相談員として回答しています。
本記事では、動画で配信している『新規事業お悩み相談室』を1分で読めるダイジェスト版としてお届けします。
今回いただいた相談は「社会的意義の高い事業の持続可能性について」です。
質問者:
再生可能エネルギー業界・Dさん
相談の背景や理由:
私は大企業で新興国向けに社会的意義の高い環境事業に取り組んでいます。現在、この事業は補助金や出資者の支援に大きく依存しており、直接的な利益は正直まだ大きくありません。事業の社会的価値は認識していますが、補助金や出資者以外で持続可能な収益モデルを構築する方法に悩んでいます。事業を継続的に成長させるためには、どのような戦略やアプローチを考えるべきでしょうか?利益を生み出しつつ、社会的貢献を続けるバランスの取り方についてアドバイスをいただけないでしょうか?
角:本日のご相談は再生可能エネルギー業界Dさんから「社会的意義の高い事業の持続可能性について」についてです。こちら、新興国向けにということですので、蛯原さんからご意見を伺ってもよろしいでしょうか?
蛯原: これは我々の投資先のインドや東南アジアなどの新興国も含めて、「新興国でのベンチャー投資あるある」です。インターネットの世界での競争が激化する中、多くの企業がリアル産業のDXに力を入れています。特に新興国では、金融アクセスや医療アクセスなどを提供するいうことも含めて社会的意義の高い事業がたくさん生まれています。しかし、おっしゃる通り、マネタイズは非常に困難です。一人あたりの単価が低かったり、そもそもお金を払うという文化がなかったりするためですね。
そこで多くのスタートアップが取り入れているのが、事業にフィンテック、特にレンディング(貸付)の要素を組み合わせるという手法です。これはもはや常道ですね。新興国では直接的な対価を得るのが難しいので、多くのベンチャーが別の方法で収益化を試みています。
一つは、事業にフィンテック、特にレンディング(貸付)の要素を組み合わせることです。例えば、物流スタートアップが、運賃だけでは利益が低い場合に、ドライバーにレンディングを提供することで収益を確保します。農業分野でも、農家が資材購入に困っていることが多いので、レンディングを組み込むことで、サプライチェーン全体の流通を円滑にしながら収益を上げることができます。
もう一つは、マネタイズのポイントをずらすことです。提供するサービスそのものでお金を稼ぐのではなく、そこから得られる「何か」を別の市場で収益化します。たとえば、ある環境関連のスタートアップは、二酸化炭素の排出削減を支援するサービスを提供しています。削減に成功した企業からはお金をもらいにくいため、代わりにその削減量を国際基準でモニタリングし、カーボンクレジットとして発行して大手企業に売ることで収益を上げています。いずれにしても、質問いただいたように新興国で直接的に対価を得るのはまだまだ難しいところがあるので、今お話ししたような手法を参考にしていただけたらと思います。
角:すごく具体的な例が出てきましたね。レンディング、あるいはズラすというやり方ですね。後者だと少し難しそうに感じますがどうなんでしょうか?
蛯原:そうですね。後者はなかなか難易度が高いです。だからレンディングの方は結構いろんなスタートアップがやっているので、逆に言うと新興国のスタートアップのデフォルトっぽい感じになってますね。
角:なるほど。まずはそちらのアプローチから考えていくということですね。非常に具体的なご提案をありがとうございます。村上さんはいかがでしょうか?
村上:いや、もう専門家のおっしゃる通りだなと思いますよね。僕から付け加えることもないんですけども、レンディングはたしかにそうだなと思いながら聞いていました。
日本でも農家向けの「収穫期払い」のような支払い方法があります。たとえば、ホームセンターのコメリは、農家専門のコメリカードで収穫期払いの選択肢を用意しています。これは、サラリーマンのボーナス時期に合わせるのではなく、農家の収穫時期に合わせて支払いのタイミングをずらすことで、彼らにとって使いやすいサービスに最適化しているわけです。また、新興国では「小分け」が有効な戦略となることがあります。高価なボトル入りのシャンプーは買えなくても、1回分のパウチなら買えるといったように、細かく分けることで需要を生み出せます。マンダムがシェービングフォームを小分けパックで販売し、売店で手軽に買えるようにしたことで初期の顧客を獲得した事例も有名です。このように、状況に応じて前提を変え、大きなものを小さくするなど、さまざまなアプローチが考えられますね。
角:なるほど。
村上:以前、IoTの仕事をしていた際、ある国で電気代を携帯電話のようにチャージして払うシステムに関わっていました。かつての携帯電話のパケット代のように、銀行口座を持たない人々が、プリペイド方式で100円や200円といった少額をチャージして使っていて、この仕組みを電気代や光熱費にも応用できないかと考えました。そこで、安価なスマートメーターを開発して、携帯電話のようにチャージして電気を使うシステムを作ったんです。残高がなくなると電気が止まるため、電気を使い続けたければ、毎日少しずつでもチャージを続ける必要がありますが、この仕組みは電気の未払いをなくすことができ、貸し倒れリスクをゼロにできます。IoT機器と無線通信技術が安価になったおかげで実現できた事例です。
角:いろんなお金の取り方が実はあるんですっていうのが、今回の学びになっていればいいなと思いますね。お金がどうまわるようにすればいいのかというところですよね。使っているサービスなどが使えなくなってしまうと困るからちゃんとお金を払って使えるようにしようという気持ちになる。そういうことをうまくビジネスの中に取り込んでいくということを考えていくといいんじゃないかと思います。難しいと諦めるのではなくて、そこからもう一段掘り下げて考えてみるのが答えに近づく道なのかなという部分をお分かりいただけたらいいなと思います。ということで、再生可能エネルギー業界Dさん、参考にしていただければと思います。
回答のまとめ
1.新興国における収益化の困難さと定石的アプローチ:
・新興国では単価の低さや「お金を払う文化」の不在から、社会的意義の高い事業であっても収益化は難しい
・そのため多くのスタートアップは「レンディング(貸付)」を組み込むことで収益を確保する。物流や農業などの分野で資金不足を補う仕組みとして有効であり、定石的な手法となっている
2.マネタイズのポイントをずらす戦略とその難易度:
・サービス提供自体ではなく、その副産物を活用して収益化する事例がある(例:環境系スタートアップが削減した二酸化炭素をカーボンクレジット化し大企業に販売する)
・ただし難易度は高く、多くの企業にとって現実的な第一歩はレンディングの方である
今回ご紹介した内容は、以下のリンクから動画で視聴できます。